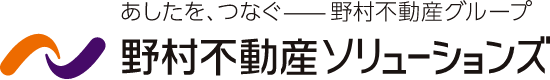会計・税・鑑定
最高裁令和4.4.19判決が 不動産取引に及ぼす影響と対策

本稿では、「最高裁令和4.4.19判決の要旨」を取りまとめ、同事案の理解に必要な「不動産取引価額と通達評価額の乖離の理由」を明らかにし、その乖離の中での「不動産取引を利用した節税策の規制」の内容を説明し、その規制の中核となる「評価通達6項の意義と適用要件」を考察し、まとめとして、今後の「不動産取引への影響と対策」を検討する。
Ⅰ.はじめに -問題の所在-
相続税法は、相続等によって取得した財産の価額を「時価」によることとしており(相法22)、その「時価」は、学説、判例では「客観的交換価値」(不特定多数の者の間で通常取引される価額)であると解されている。しかし、「時価」といっても「客観的交換価値」といっても、そのような抽象的な概念は把握(算定)し難いので、一般(実務)的には、国税庁が定める財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)が定める評価額(評価方法)(以下「通達評価額」という。)に基づいて納税申告又は課税処分が行われている。
ところで、評価通達6項では、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めている。この規定は、例えば、納税者が相続した宅地の価額を国税庁が定める路線価で評価して納税申告を済ませても、その路線価に基づいた評価額が「著しく不適当」と認められると、修正申告等が求められることを意味している。そのため、納税者側からすると、評価通達6項の規定が、租税法律主義が保障する予測可能性に反し、又は憲法上の平等原則に反するということで、その規定自体の違法性を問題にしたり、その規定に基づく課税処分の違法性を争うことになる。そして、近年では、特に、不動産取引を中心に評価通達6項に基づく課税処分の違法性を争う訴訟事件が増加している。その中で、最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決(令和2年(行ヒ)第283号)(以下「最高裁令和4.4.19判決」という。)が、最高裁判所として初めて、評価通達6項に基づく課税処分の適法性を認め、かつ、その法的根拠(理由)を明確にした。
そのため、課税当局が評価通達6項の適用を一層活用する可能性があるということで、特に、不動産業界では、不動産取引全体に悪影響が生じるのではないかという不安が流れ、動揺しているようである。しかし、この問題は、単なる「傾向と対策」で解決するものではなく、相続税法上の「時価」の本質、評価通達の構造上の問題と6項の位置付け、その構造上の問題から生じる節税策等に対する規制措置とそのあり方、その規制措置の一環としての評価通達6項の意義と裁判例の傾向等を正確(冷静)に把握した上で、今後の対策を講じておかないと解決できないことになる。
そこで、本稿では、まず、「最高裁令和4.4.19判決の要旨」を取りまとめ、同事案の理解に必要な「不動産取引価額と通達評価額の乖離の理由」を明らかにし、その乖離の中での「不動産取引を利用した節税策の規制」の内容を説明し、その規制の中核となる「評価通達6項の意義と適用要件」を考察し、まとめとして、今後の「不動産取引への影響と対策」を検討する。
Ⅱ.最高裁令和4.4.19判決の要旨
(1) 事案の概要
(イ) 被相続人Aは、平成24年6月17日に94才で死亡した。Aの死亡により、Aの妻K(訴外)、長女X1(原告、控訴人、上告人)、長男X2(原告、控訴人、上告人)、二男T(訴外)及び養子X3(Tの長男、原告、控訴人、上告人)(以下「本件共同相続人」といい、原告等3名を「Xら」という。)は、Aを相続(以下「本件相続」という。)し、本件相続に係る財産を取得した。
本件相続に係る相続財産には、杉並区所在の土地(以下「本件甲土地」という。)及び同土地上に存する建物(以下、本件甲土地と併せて「本件甲不動産」という。)並びに川崎市所在の土地(以下「本件乙土地」という。)及び同土地上に存する建物(以下、本件乙土地と併せて「本件乙不動産」といい、本件甲不動産と本件乙不動産を併せて「本件各不動産」という。)が含まれていた。本件各不動産は、Aの遺言により、X3が取得した。
(ロ) Aは、平成21年1月30日、本件甲不動産をC社から総額8億3,700万円で購入し、同日、M銀行から6億3,000万円を借り入れた。また、Aは、平成21年12月25日、本件乙不動産をG社から総額5億5,000万円で購入し、同日、M銀行から3億7,800万円借り入れ、同月21日、Kから4,700万円を借り入れた。
なお、X3は、平成25年3月7日、Sに対し、本件乙不動産を総額5億1,500万円で売却した。
(ハ) Xらは、平成25年3月11日、本件相続税の申告(以下「本件申告」という。)をしたが、本件各不動産の価額を評価通達の定めに従い、本件甲不動産の価額を2億4万円余及び本件乙不動産の価額を1億3,366万円余と評価し(以下「本件各通達評価額」という。)、相続財産の総額10億156万円余、債務等の額9億9,706万円余、相続税の総額0円とした。
これに対し、処分行政庁は、平成28年4月27日、本件各不動産の価額を評価通達6項に基づいて評価することとし、不動産鑑定士の鑑定評価額に基づき、本件甲不動産の価額を7億5,400万円及び本件乙不動産の価額を5億1,900万円(以下「本件各鑑定評価額」という。)と評価し、相続財産の総額18億8,581万円、相続税の総額2億4,049万円余とする各更正(以下「本件各更正」という。)等をした。Xらは、本件各更正等を不服として、前審手続を経て、平成29年11月22日、国(被告、被控訴人、被上告人)に対し、当該各処分の取消しを求めて、本訴を提起した。本訴では、主として評価通達6項を適用した本件各更正の違法性が争われた。
そして、一審の東京地裁令和元年8月27日判決(平成29年(行ウ)第39号)及び控訴審の東京高裁令和2年6月24日判決(令和元年(行コ)第239号)がXらの請求を棄却したため、Xらが、上告したというものである。
(2) 上告審判決要旨
上告棄却(請求棄却)
原審は、上記事実関係等の下において、本件各不動産の価額については、評価通達の定める方法により評価すると実質的な租税負担の公平を著しく害し不当な結果を招来すると認められるから、他の合理的な方法によって評価することが許されると判断した上で、本件各鑑定評価額は本件各不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるからこれを基礎とする本件各更正は適法であり、これを前提とする本件各賦課決定も適法であるとした。所論は、原審の上記判断には相続税法22条等の法令の解釈適用を誤った違法があるというものである。
相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとするが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。そして、評価通達は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。
そうであるところ、本件各更正に係る課税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件各不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるというのであるから、これが本件各通達評価額を上回るからといって、相続税法22条に違反するものということはできない。
他方、租税法上の一般原則としての平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される。そして、評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。もっとも、上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。
これを本件各不動産についてみると、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きな乖離があるということができるものの、このことをもって上記事情があるということはできない。
もっとも、本件購入・借入れが行われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2,826万円余にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になるというのであるから、Xらの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきである。そして、A及びXらは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想されるAからの相続においてXらの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる。そうすると、本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。
したがって、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するということはできない。
以上によれば、本件各更正において、所轄税務署長が本件相続に係る相続税の課税価格に算入される本件各不動産の価額を本件各鑑定評価額に基づき評価したことは、適法というべきである。所論の点に関する原審の判断は、以上の趣旨をいうものとして是認することができるので、原告(納税者)の論旨は採用することができない。
Ⅲ.不動産取引価額が通達評価額と乖離する理由
(1) 乖離の態様
前掲最高裁令和4.4.19判決の事案においては、札幌に居住していた被相続人Aが、90才を過ぎてから相続税対策のために比較的取引価額と評価通達上の評価額の格差が大きい首都圏に所在する本件各不動産を総額13億8,700万円で取得し、その購入代金の大部分をM銀行から借り入れたものである。そして、本件各不動産の評価通達上の評価額が3億3,370万円余であったというのであるから、Aは、本件各不動産の取得によって、10億5,330万円余の相続財産を圧縮することができることになる。その結果、本件相続によって本件共同相続人は、本件各不動産取得前では、6億円超の相続財産が見込まれたにもかかわらず、本件申告の段階では相続税の負担を要しなかったというものである。
また、当該事案においては、本件各不動産の取得と本件相続開始時のタイムラグが、本件甲不動産については3年5月、本件乙不動産については2年7月あり、本件乙不動産を取得したX3が本件相続開始後9月後に5億1,500万円で譲渡しており、本件各不動産の取得に係るM銀行の融資の際の貸出稟議書に相続税対策が明確にされていたこと等の事実が認められる。
また、最近の裁判例では、東京地裁令和2年11月12日判決(平成30年(行ウ)第546号)及び東京高裁令和3年4月27日判決(令和2年(行コ)第242号)の事案では、相続開始約2月前に賃貸用マンションを約15億円(全額借入金で調達)で取得し、その賃貸用マンションを通達評価額4億7,761万円余で評価して、相続税を申告したことに対し、評価通達6項を適用(鑑定評価額10億4,000万円で課税)した課税処分が適法とされている*[1]。このほか、近年では、タワーマンションの取得による取得価額と通達評価額の乖離を利用した節税スキームの是非が問題とされている*[2]。
元々、相続税等における不動産の取引価額と通達評価額の乖離を利用した節税スキームは、昭和の末期から平成の初めにかけての土地バブルの頃は主として土地を対象に行われてきたが、最近では、前述の各事案に見られるように、賃貸マンションやタワーマンションのような土地と建物が合体となった物件が中心になってきている。
なお、このような不動産取引価額と通達評価額の乖離の問題は、法人(会社)が不動産を取得し、当該法人の株式等を純資産価額方式等で評価する場合にも、同じように生じることになる。例えば、前掲の最高裁判決のような事案について、同族関係の会社が行った場合において、当該会社の株式の価額を純資産価額方式で評価すると、当該株式の価額はほぼ零円で評価されることになる。また、同族の資産管理会社が土地等を大量に取得して当該株式を類似業種比準価額で評価すると、評価額を大幅に圧縮することが可能になる。もっとも、このような会社が不動産等を取得して株式の価額を引下げる方法については、別途評価通達上の規制(「評価通達」185かっこ書、189等参照)があるので、それらの規制との関係が問題となる。
(2) 評価基準制度(標準価額)との関係
評価通達1(2)は、「時価とは、……不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」と定めている。この規定の前段の規定は、いわゆる客観的交換価値を意味するものとして、相続税法上の「時価」の意義(解釈)として一般的に容認されている。他方、後段の規定は、評価通達が行政命令としての機能が求められるが故に、主として、評価の統一性(ひいては、課税の公平性)、便宜性等を図るために、各財産ごとに評価額(評価方法)を画一的に定めることを意図している。また、評価通達が相続税法の解釈通達として存在しているが故に、通達評価額は、相続税法上の「時価」を上回らないように、評価の安全性にも配慮せざるを得ないことになる。
かくして、土地、家屋のような不動産の相続税法上の「時価」については、課税実務では、評価基準制度に基づく標準価額によって評価されることになる*[3]。この標準価額については、前述の評価通達に求められる各種の要請を受けることになる。例えば、土地(宅地)については、路線価方式に代表されるように、公示価格と同様、その年の1月1日を評価日とし、標準宅地について、公示価格水準の8割相当額で設定された路線価に基づいて評価される。また、家屋については、固定資産税評価額に一定の倍率を乗ずることで評価されることになっているが、現在、その倍率は1.0とされている。この固定資産税評価額も固定資産評価基準制度に基づいて評価されることになっているが、相応の評価の安全性が図られている。そのため、通達評価額と取引価額との間には、相応の乖離が生じることはやむを得ないことである。また、そのことは、通常の相続税や贈与税の課税実務において容認されてきたところである。そして、このような通達評価額は、所得税法及び法人税法における「価額」の評価においても、実務上の拠り所となっている。
しかしながら、このような乖離を利用した節税スキーム等が課税上又は評価上看過し難いということであれば、前述のような評価基準制度を採用せずに、相続税法上の「時価」を客観的交換価値と解して、当該解釈を当事者(納税者、国税庁職員)に委ねれば可とする考え方もある。しかし、それでは、相続税法等の執行(申告、課税)が困難になるわけであるから、当該制度を是とした上で、当該制度の弊害を是正するための何らかの規制が必要となる。
*[1] この事案の東京高裁判決についても上告(上告受理申立て)されたが、最高裁判所は、前掲最高裁令和4年判決の同日に上告不受理にしている。
*[2] タワーマンション問題については、品川芳宣「最近の相続税節税策(スキーム)の真贋を問う!」野村資産承継 創刊号(2015年)76頁、同「財産(資産)評価の実務研究 第23回」資産承継2022年4月号145頁等参照
*[3] 評価基準制度をめぐる問題については、品川芳宣「租税法律主義と税務通達」(ぎょうせい 平成16年)119頁以下、同「財産(資産)評価の実務研究 第3回」資産承継2018年春号198頁以下等参照
Ⅳ.不動産取引を利用した節税策の規制
(1) 法律による規制
まず、昭和末期の土地バブルの最盛期において、土地等の不動産の取引価額と評価通達上の評価額の乖離を狙った節税策(税逃れ)が横行した。もちろん、当時も評価通達6項は存在していたが、課税(立法)当局は、立法上の措置でそれらに対処することとした。すなわち、昭和63年12月末に成立した租税特別措置法69条の4(以下「旧措置法69条の4」という。)は、被相続人が、相続開始3年以内に土地等又は建物等(居住用を除く。)を取得している場合には、相続税の課税価格に算入すべき当該土地等又は当該建物等の価額をそれらの取得価額とする旨定めた。このように、相続税の課税価格を「取得価額」に固定すること(すなわち、「時価の法定化」)は、当該財産の取引価額が上昇すれば納税者にとって有利に働くし、下落すれば不利に働くことになる。このことは「時価」を法定(固定)することの矛盾を惹起することになる。
かくして、平成に入ってバブル経済の崩壊により地価等が暴落したため、大阪地裁平成7年10月17日判決(行裁例集46巻10・11号942頁)の事案では、約23億円で取得した土地が相続開始時に約9億円に暴落したにもかかわらず、約13億円の相続税額を課税する課税処分が行われ、当該処分の合憲性が争われ、同判決は、旧措置法69条の4の規定は合憲であるが、同規定を適用した課税処分は違憲状態になる旨判示し、当該課税処分を取り消した。そして、上訴審の大阪高裁平成10年4月14日判決(訟務月報45巻6号1112頁)及び最高裁平成11年6月11日第二小法廷判決(税資243号270頁)も、前掲大阪地裁判決を支持している*[1]。なお、旧措置法69条の4は、平成8年度税制改正において廃止された。
(2) 通達による規制
前記3で述べたように、評価通達では、相続等によって取得した不動産等の「時価」を標準価額によって評価しているが故に、それによる弊害が生じることを想定して、同通達の中で、当該標準価額による評価を制限することを定めている。その制限を包括的に定めたものが、評価通達6項である。それ以外にも、個別に次のような制限規定(措置)が設けられてきた。
すなわち、前述したように、旧措置法69条の4の制定によって相続税における不動産取得の節税策が封じられたため、不動産取得による節税策は、贈与税において一層活発化することになった。例えば、親が1億円で取得した土地を子に評価通達の評価額2,000万円で譲渡(又は負担付贈与)した場合に、同通達がその2,000万円を「時価」と定めている(「評価通達」1(2))が故に、みなし贈与課税(相法7)は適用されないと解されていた。そこで、国税庁は、「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について」(平成元年3月29日直評5ほか、以下「負担付贈与通達」という。)を発遣した。負担付贈与通達は、土地等及び家屋等のうち、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得したものの価額は、評価通達の規定にかかわらず、当該取得時における通常の取引価額(譲渡者の取得価額がそれに相当するときには、当該取得価額)によって評価することとした*[2]。
また、不動産の取得による節税策は、個人間の取引にとどまらず、法人においても行われていた。例えば、純資産価額(相続税評価額)100億円の会社が150億円借金をして土地を取得すると、当該土地の相続税評価額が50億円であれば、当該会社の純資産価額方式による株式評価額が零となるので、その土地取得後全株式を子に贈与しても贈与税は課税されないことになる、という事例もあった。そのため、国税庁は、平成2年8月3日付で評価通達を改正し、評価会社が課税時期前3年以内に取得等した土地等及び家屋等の価額を課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額(取得価額)が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができる(「評価通達」185かっこ書)こととした。
このような措置については、類似する封じ策について、法律の定めと通達の定めが混乱しているという批判があり、その批判は、租税法律主義の建前上、全てを法律によって律すべきである旨の主張にもつながる。また、この批判は、旧措置法69条の4に定める「3年しばり」と評価通達185項に定める「3年しばり」は同じであるから、前者が平成8年に廃止された以上後者も廃止すべきである旨の主張を惹起することになった。しかし、「時価」の取扱いは、本来、「時価」の動向によって対処できる通達によって行われるべきものであって、法律で「時価」を固定する方が問題となることは、旧措置法69条の4が廃止されたことが証明している。よって、評価通達185項の「3年しばり」を廃止すべきとする批判も、的を射ていないことになる*[3]。
また、旧措置法69条の4及び評価通達185項に定める「3年しばり」において、何故「3年」かということが問題となる。この「3年」については、課税時期前3年以内の取得価額が「時価」に近似していることと、当時の節税策が銀行から借金して不動産を購入するという手法であったことから、当時の借入金の利息5~10%という金利負担を考慮すると、課税時期3年以上前に不動産を取得しても、当該節税策が成立しなくなるということを考慮したものである。しかし、この「3年しばり」は、本件にも関わることであるが、納税者に対して不動産を取得して「3年」を越えたら不問に付されるという予測を与えていることと、最近の超低金利に対処できないということの問題を惹起している。そのため、「3年しばり」の妥当性が問題となる。もっとも、節税等のための不動産取得と課税時期との間の期間の長さを全く無視すると、評価通達において標準価額制度を設けた趣旨が没却される。
そのほか、通達評価額と取引価額との乖離から派生する問題として、複層化信託の受益権の評価問題がある。複層化信託の受益権の価額については、評価通達202によって評価されることになるが、本受益権の価額を低く評価して当該低評価額で当該信託財産を早期に子息等に贈与することを目的とする。その弊害を防止するため、平成12年に現行の評価方法に改められているが、なお節税策の手段に利用されることがある*[4]。更に、資産管理会社を設立して、当該会社が不動産を多額で取得して、当該会社の株式評価額を引き下げる手法も横行したこともあったので、平成2年の評価通達の改正によって規制措置がとられている(「評価通達」189-4等参照)。
*[1] 品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第三版」(大蔵財務協会 平成26年)906頁等参照
*[2] このような措置は、ほかにも、平成2年8月の評価通達の改正において、上場株式等についても通達評価額と取引価額の乖離を利用した節税策を封じるために、評価通達169(2)の規定等が設けられている。
*[3] 詳細については、品川芳宣「措置法69条の4の廃止と評価通達の関係」税理1996年5月号18頁参照
*[4] 詳細については、品川芳宣「財産(資産)評価の実務研究 第25回」資産承継2022年10月号登載予定
Ⅴ.評価通達6項の意義と適用要件
(1) 評価通達6項の存在意義
前述したように、評価通達が採用している評価基準(標準価額)制度の下では、当該標準価額と取引価額との乖離から時には看過し難い弊害が生じることがある。そのため、前記4で述べたように、法律又は通達において、所定の場合には、当該財産に係る標準価額による評価を制限し、個別に評価する措置を講じてきた。しかし、このような個別的な措置については、評価技術的な見地等からみて全ての事項について定めることができるわけではなく、現在の各規程も固定的な定めによらざるを得ない。そのため、評価通達の各定めの間隙をついた新たな問題が生じることになるので、評価通達6項の存在が不可欠であるとも考えられる。もっとも、現在でも、評価通達6項の存在を否定する向きもあるが、そのことは評価基準制度それ自体を否定することになるものと考えられる。しかし、評価通達6項の存在が裁判例において当初から容認されてきたわけではない。
すなわち、評価通達6項の考え方を初めて容認したのは、東京高裁昭和56年1月28日判決(税資116号51頁)である*[1]。同判決の事案では、被相続人が、市街化農地を4,539万円余で譲渡し、手付金及び内金合計1,600万円を受領し、当該農地の引渡予定日(同日残代金受領)15日前に死亡した場合に、所轄税務署長が、当該農地は売却済であるとして、相続財産の価額を当該売買代金残金請求権等とした課税処分の違法性が争われた。一審の東京地裁昭和53年9月27日判決(訟務月報25巻2号513頁)は、当該相続財産は相続開始日に引渡しが済んでいないから当該農地であり、当該農地の価額は評価通達に基づく評価額2,018万円余(申告額)であるとして、当該課税処分を取り消した。これに対し、前掲東京高裁判決は、当該相続財産は当該農地であるが、当該事案のように「特別な事情」がある場合には、当該農地の「時価」を当該売買代金で評価するのが相当であるとし、それが評価通達6項が定めていることの所為である旨判示した。
ところが、この東京高裁判決については、当時、本件でXらが主張するように、評価通達6項は納税者を救済するための規定であるとか、評価通達の適用上評価額が複数になって納税者に不利に作用するのは租税平等主義に反する旨等の批判もあった。そのこともあってか、上告審の最高裁昭和61年12月5日第二小法廷判決(訟務月報33巻8号2149頁)は、原判決の結論を維持したものの、当該相続財産の種類を当該農地ではなく、手付金等の額と売買残代金債権の合計額(当該売買代金)である旨判示した。もっとも、前掲東京高裁判決は、前記4で述べた負担付贈与通達の発遣や、評価通達185項の改正に論拠を与えることとなり、当該各通達発遣後の類似の事案において、評価通達6項を適用した課税処分を増加させることとなった*[2]。
(2) 実体要件
ところで、評価通達6項は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めているところ、この6項の適用においては、「著しく不適当」と認められるか否かという実体要件と「国税庁長官の指示」があったか否かという手続要件が問題となる。
この「著しく不適当」については、評価通達が相続税法22条に規定する「時価」を解釈・適用するために存在しているのであるから、当該財産の通達上の評価額と客観的交換価値との開差が客観的にみて「著しく不適当」と認められる場合に限定すべきであって、原則的には、租税回避を企画したか否かというような主観的要素は本来当該判断の要件にすべきではないと考えられる*[3]。もっとも、当該財産の取得に係る関係当事者が評価通達上の評価額と取引価額に代表される客観的交換価値に相当の開差があることを認識し、それを何らかの取引に利用して租税負担を減額させることは、租税回避の企画等(主観的要素)に関わることになる。また、このようなことは、評価基準制度が偶発的に生じる相続に対して課税される相続税を考慮して便宜性なり安全性に配慮していることの趣旨にも反することになる。
他方、最高裁令和4.4.19判決は、「特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは……合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。もっとも、……評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められる。」と判示し、本件事案に関しては、「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある」と判示している。
以上のことを総合的に考慮すると、評価通達6項にいう「著しく不適当」とは、通達評価額と取引価額又は客観的交換価額との間に著しい乖離があって、当該乖離に関する取引が行われ、当該取引の結果租税負担が著しく軽減し、当該軽減と当該取引との間に相当因果関係がある場合である、と考えられる。また、評価基準制度の趣旨に鑑み、当該取引と課税時期(相続、贈与の時)との間は一定期間(3年等)に限定されるべきである。
(3) 手続要件
次に、「国税庁長官の指示」の要否については、①税務通達は法源ではなくても税務官庁の職員を法的に拘束するものであること、②税務通達に反する課税処分が信義則違反、平等原則違反等に問われることがあること、③評価通達6項の適用には「国税庁長官の指示」が必要であるから余程のことがない限り同項の適用はないであろうと予測する納税者側の予測可能性を保障する必要があること等を考えると、この手続要件を欠く処分には違法性を惹起するものと考えられる*[4]。しかし、従前の多くの裁判例が*[5]、「国税庁長官の指示」の有無は課税処分の効力に影響を及ぼさないものであり、当該指示の存否を明らかにする必要がない旨判示している。また、前掲の最高裁令和4年判決に係る下級審判決も、同様な判示をしている。しかし、国税庁側がこのような裁判所の考え方に安易に同調することは、みすみす納税者側との信頼関係を失うことにもなるので、円滑な税務行政の遂行に専心している立場からは得策であるとも考えられない。
*[1] 前出*4 806頁等参照
*[2] 東京地裁平成4年3月11日判決(判例時報1416号73頁)、東京高裁平成5年1月26日判決(税資194号75頁)、東京地裁平成5年2月16日判決(同194号375頁)、東京高裁平成5年12月21日判決(同199号1302頁)、大阪地裁平成12年5月12日判決(同247号607頁)等参照
*[3] 前出*3 各書参照
*[4] 前出*3 各書参照
*[5] 東京高裁平成5年7月26日判決(税資194号75頁)、東京地裁平成9年9月30日判決(同228号829頁)、東京地裁平成11年3月25日判決(同241号345頁)等参照
Ⅵ.不動産取引への影響と対策
(1) 国税当局の対応
評価通達6項は、昭和39年に制定された「相続税財産評価に関する基本通達」以降存在していたのであるが、国税当局は、平成3年頃までは同項を節税封じのために適用することはなかった。前掲東京高裁昭和56年1月28日判決についても、法務当局の主導の下で国の勝訴が得られたのであるが、国税当局がそれを歓迎することはなかった。そのため、昭和63年に制定された旧措置法69条の4の制定についても、国税当局が通達評価額と取引価額との乖離を利用した節税策について通達をもって封じることを回避した結果であるとも言える。
ところが、平成元年に負担付贈与通達を発遣し、平成2年に取引相場のない株式の評価方法を中心とする評価通達の改正によって、同じ財産について通達評価額(評価方法)が2本建てになることが制度化されたことによって、評価通達6項を適用する課税処分が行われるようになった。そして、平成8年に前述の旧措置法69条の4が廃止されたが、国税当局は、それ以降、同条が対象にしていた不動産取引を利用した節税策が存在(横行)していたにもかかわらず、新たな通達上の措置を講じることなく、評価通達6項の適用によって対処してきた。本稿で問題にしている最高裁令和4.4.19判決の事案についても、そのような傾向の中で生じたものと言える。
以上の経緯等を考察すると、国税当局としては、評価通達6項を適用する課税処分について最高裁判所から御墨付きを与えられたものであるから、同項の適用を一層活用するようになることが予測される。それに加え、平成23年の国税通則法の改正によって税務調査に厳しい規制が行われ、かつ、当該改正を契機に国税当局にも税務調査の重要性を軽視する傾向が見受けられるため、調査能力の低下が一般に見受けられる。そうなると、調査担当者としては、安易に調査権力に依存するようになり、その調査権力の手段として最高裁令和4.4.19判決を利用することも予測され、現に、そのような傾向が見受けられるようである。そして、そのような傾向は、単に個人の不動産取引に限らず、法人の不動産取引に及ぶことが考えられる。
(2) 対策
イ. 取引段階
不動産取引は、多様な経済目的のために行われるのであって、節税目的はその一つに過ぎない。また、他の経済目的のために行われる不動産取引であっても、結果的に節税を伴うこともあり、それが税務上の否認の対象となることもある。そうなると、不動産取引については、前述の国税当局の対応をも考慮し、その取引が節税に関わるものであれば、従前以上に慎重な検討を要することになる。例えば、相続税対策のために不動産を取得する場合であっても、長期的な戦略が必要であって、相続が近づいたからといってあわてて金融機関から借入れをして不動産を取得するようなことは厳に控えるべきである。このような不動産取得について、従来であれば、取得後3年を経過すれば可とする考え方もあったが、そのような3年ルールも前述の最高裁令和4.4.19判決の事案に照らすと、適用しないようである。しかし、無制限に長期になることは、前述の評価基準制度の趣旨を没却することになるので、一定期間経過したら可とするルールが構築されるべきである。
また、同族の不動産管理会社が不動産を取得して当該会社の株式の価額を純資産価額方式で評価する場合には、当該取得後3年間は、当該取得不動産の価額が「通常取引される価額」(通常、当該取得価額)で評価されることになっている(「評価通達」185かっこ書)が、その3年が経過した後に相続・贈与があった場合にも、評価通達6項を適用して「通常取引される価額」によって評価される可能性も否定できない。しかし、この問題は、評価通達で3年ルールを明確にしているわけであるから、国税当局による評価通達6項の適用は一層ハードルが高いものと考えられる。
ロ. 調査・争訟段階
前述のように、不動産取引の段階で慎重な節税方法を採用するにしても、あるいは、そのような方法を検討しない場合もあるであろうから、いずれの場合にも、納税者の当該取引に基づく相続税の申告又は贈与税の申告について、税務調査の段階で評価通達6項の適用が問題になることも考えられる。そのような場合には、結局、前述してきた評価通達が定める評価基準制度の構造上の問題を理解し、かつ、それに関連する節税策に対する規制措置や関連裁判例を分析・検討し、調査担当者に対する冷静な対応が求められることになる。この場合、調査段階での対応は、当該事案か争訟に適うのか否かも検討し、どの段階まで争うことが可能か(不服申告での段階か、訴訟まで行けるのか)についても、検討する必要がある。それらを総合的に検討・判断した上で、修正申告に応じるべきか、更正・決定を受けて争うべきかを検討しなければならないことになる。また、争訟段階においても、審査請求まで行うのか、取消訴訟まで進むのか、等について専門的知見が求められることになる。
本資料はご参考のために著者及び野村不動産ソリューションズ株式会社が独自に作成したものです。本資料に関する事項について貴社が意思決定を行う場合には、事前に貴社の弁護士、会計士、税理士等にご確認いただきますようお願い申し上げます。また推定値も入っており、今後変更になる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、本資料のいかなる部分も一切の権利は野村不動産ソリューションズ株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。
品川 芳宣
株式会社野村資産承継研究所 名誉顧問

<経歴> 国税庁直税部資産評価企画官(昭和63年~平成3年)、国税庁徴収部徴収課長(平成3年~4年)、国税庁徴収部管理課長(平成4年~6年)、高松国税局長(平成6年~7年)、筑波大学大学院ビジネス化学研究科教授(平成7年~17年)、早稲田大学大学院会系研究科教授(平成17年~24年)を経て、現職(=筑波大学名誉教授、日本医師会医業税制検討委員会専門委員、日本商工会議所税制委員会特別委員、租税法学会理事、税務会計研究学会理事、税理士法人大手町トラスト代表社員)。著書・論文多数。(2022年4月時点)
企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから