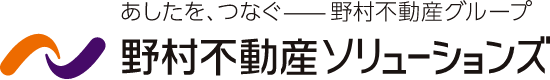トレンド
【連載】2030年の東京不動産(第2回)
~2030年の社会と観光・ホテル、商業施設の動向~

2013年以降活況を呈してきた東京の不動産。20年の2月から世界を席巻したコロナ禍は、日本の経済や社会に大きな影響をもたらしたが、いっぽうでコロナ禍がきっかけになり、人々の生活は大きく変化した。そうした社会の変化に対し、東京の不動産はどのような変化をみせていくのか、本稿では現在から8年後の2030年を見据えた東京の不動産について考えてみよう。
Ⅱ-Ⅰ.観光立国に舵を切った日本
日本の未来は何で生きていくのだろう。
ものづくり大国ニッポンなどと言われ、世界から称賛されたのは90年代まで。現在は一人当たりGDP(購買力平価換算)で世界30位。世界の企業時価総額ランキングでも、ベスト30に入る日本企業が皆無といった惨憺たる状況にある。
こうした時代環境のもと「日本は観光立国へ」こんな旗印が掲げられだしたのは2003年、当時の小泉純一郎内閣が主宰した観光立国懇談会だ。この流れは同年4月からのビジットジャパン事業となって始動し、2007年には観光立国推進基本法が制定される。東日本大震災以降、訪日外国人数は増加を続け、コロナ禍前だった2019年には3000万人を超えるに至っている。
日本ほど観光資源に恵まれた国はない。国土が南北に長いため、季節ごとの様々な自然景観が楽しめる。島国で海岸線が長く、急峻な山岳があり、河川が多く、水流が豊かだ。また歴史的建造物が多く、国内交通機関が充実している。鉄道網、道路網は密で、どこに行くにも多くの時間を要さない。国内を比較的短時間で移動ができることは、観光にとって極めて重要なポイントである。鉄道や道路の存在は、観光、旅行が容易にルート化できるからだ。こうした地の利、利便性の高さを多くの日本人はあたりまえのことだと思っているが、2030年を迎える日本ではこの強みを生かした、観光・宿泊業戦略にはおおいに期待ができるのだ。
日本は食文化が発達し、芸術作品も多い。スキーなどのウィンタースポーツにも適する。世界が注目してもおかしくはない。
日本人自体も旅行好きだ。江戸時代にはお蔭参りとも呼ばれる伊勢神宮への参拝客は年間で数百万人にものぼったといわれる。また春の桜、夏の避暑、秋の紅葉など自然を身近に感じてこれを愛でる日本人は、何かにつけ出歩くのが好きな国民だ。
観光が日本のキラーコンテンツの一つであることは間違いない。ただこれをもって観光立国、つまり日本の代表的な産業として大いに成長していくのかと言われれば、全くそのような対象ではないことは明らかである。
コロナ前でもインバウンド関連の観光消費額は約4兆8000億円程度。国のGDPの1%にも満たない。産業としての規模は小さすぎてお話にならない。逆にこんな小さな産業に活路を求めるのは、明らかに日本の衰退を物語っている。
Ⅱ-Ⅱ.観光関連不動産の未来は明るい
それでも観光関連の不動産の未来は明るい。伸び筋は、中長期滞在型の高級リゾートホテルである。
コロナ禍でインバウンドの客足が途絶える中で奮闘したのが高級リゾートホテルだった。私の会社でプロデュースした大分県別府温泉のインターコンチネンタルリゾートは、国内富裕層が多く訪れ、稼働率こそ目標を下回ったものの、平均宿泊単価は高水準を保ち、日本国内に高級リゾートホテル需要が存在することを裏付けた。
コロナ後は、これにアジアを中心とした富裕層が加わることで客層に厚みができることが予想される。温泉地においても高級リゾートが誕生し始め、ニセコや白馬ではスキーリゾートが隆盛となる。観光やアクティビティを基軸とした中長期滞在の顧客が日本の観光、リゾート関連の未来を潤すことは確実だ。
現実として外資系高級ホテルブランドはコロナ後の日本マーケットに自信と期待をにじませている。あるホテルブランド首脳はこう語る。
「コロナ禍でも日本のリゾート地にある外資系高級ブランドは成績が悪くなかった。理由は国内にこうしたホテルを楽しむ需要が育っていること。ソウルや香港、シンガポールなどでは顧客のほとんどがインバウンド。日本は国内需要だけでもかなり賄えることが証明された。インバウンドが戻る2030年頃には市場はさらに活況になっているだろう。
Ⅱ-Ⅲ.ライフスタイルの変化で視界不良なビジネスホテル業界
いっぽう同じホテルでもビジネス系ホテルの未来は不透明だ。
働き方の変容は、基本的に面談して商談を進めるビジネススタイルから、本当に必要な面談以外はオンライン上で済ませるスタイルに確実に変容する。業績報告会や定例化している本社からの支店訪問などもオンラインですませるようになる。
すでに転勤や単身赴任を事実上廃止する企業が出始めた中、ビジネス需要だけに頼ったホテルの未来を見通すことができない。ホテルの未来は増え続けることが予想される観光客の取り込みを目指すことになる。
また注目すべきは、ホテルにおけるホスピタリティの変化だ。おそらく「おもてなし」といった定義は、一部の高級ホテルと旅館に限定したものになるだろう。ビジネスホテルではチェックイン手続きはすでにATMによるものが増えてきたが、ビジネスホテルで特異なサービスを求める需要は消滅するだろうし、逆に高度な技術を伴った対面のホスピタリティには多額の料金が請求される時代がやってくる。
では観光需要を取り込めないホテルはどうなるだろうか。限りなく中長期滞在用のレジデンスとなる。働き方の変容とは、みんなが在宅で働くということではない。多様な働き方は、たとえば一つのプロジェクトが成就するまでホテル内に引き籠って仕上げるなどという働き方を行う客が現れることを意味している。住宅とホテルの境界線は限りなく薄くなっていくだろう。
Ⅱ-Ⅳ.魅せる・楽しむ商業施設の未来像
商業施設の未来は大きく変わる。変化の引き金を引いたのはEC(電子商)取引だ。日常品、汎用品の多くはすでに楽天やアマゾンに注文して調達する形態が定着している。
この流れは今後加速こそすれ、元に戻ることはない。商業施設は買い物という行為を楽しむものに変わり、目的のものを買う(そのほとんどがECで購入できてしまう)のではなく、商業施設に出かけることが、一つのイベント、あるいはハレの場を楽しむものになるだろう。
すでに静岡県御殿場や千葉県木更津などに展開するアウトレットモールはその先駆け的存在だ。買い物はあくまでも「ついで」となり、富士山を眺め、あるいは東京湾に沈む夕陽を楽しみながら行うものにと変容している。長野県軽井沢にあるプリンスモールには、東京などから犬を連れたファミリーが来て、芝生の広場での滞在を楽しむ。そしてこうした生活の充実感を胸に、そのときの気分で品物を選ぶ。
お気に入りのブランドがあっても、良い品がたまたまあれば買うし、なければ買わない。商業施設は山でも、海でも、高原でもいろいろなアイテムを借りてきてショウを演出する機能を前面に打ち出したエンターテイメント施設に変貌する。

このことは都心部にある百貨店においてもあてはまる。百貨店の未来は生活シーンの演出にある。そのためには現在のようなハコ型の店舗が本当によいのか再考が迫られるようになる。
大きなフロアの棚にいろいろな商品がそれぞれ自己主張を繰り返すのではなく、店に来た客が、そのままドラマや映画の主人公になったような感覚で買い物を楽しめる空間演出がなされる。客の好みはその時の気分、体調でも変わる。百貨店では客の生活設計を共に考え演出し、客が知りえなかった世界へと導く、高度に進化した販売手法が採用される。
都心にいるときの私、リゾート地での私、家で寛ぐときの私。それぞれの生活シーンを服装や雑貨などのアイテムから入るのではなく、客が置かれた環境や気分、そしてこれからの私を演出する、いわば客のパートナーとしての存在感を高めていくことに新しい商機を得ていくだろう。
百貨店は業態として古臭く、廃れていくといった指摘があるが、本質を外れた議論である。オンラインサイトが、うるさいくらいにネット上で売り付けてくるアイテムは、客が見ていたネット記事や商品検索したアイテムをデータ化して、「あなたはこれが好きなはず」と勝手に解釈して送りつけてくるものにすぎない。百貨店こそは客と対面で向かい合い、客の人生を一緒に伴走することができる業態だ。のこのことネットの世界に迷い込むのはネット側の思うつぼだ。
だからすべての客に向かい合う必要はない。ただ客のほうから店に来れば何かがある。自分の知らない世界が広がっているという演出が求められるのである。その形態はハコや上空へと延びる空間というよりも、一つの街、ビレッジへのいざないであろう。
街全体がお店であり、全体が寛げる空間である。コンセプトを明確にしたショウハウスに滞在できてもよい。未来の百貨店はテナントを並べての大家業ではなく、空間全体が劇場のような舞台であることが求められている。もちろん主役は客だ。脚本、演出が百貨店だ。
Ⅱ-Ⅴ.飲食施設の形態進化、文化芸術の花が咲く
飲食施設の在り方も激変する。なぜなら会社という村が都心から多く消滅してしまうからだ。
村民はばらけて好き勝手なところに住むようになる。しかしだからといって多くの人々が地方に散ってしまうかと言えばそうでもない。生活に都市的な機能、快適さを求める傾向には変わりがないからだ。一部の人たちは相変わらず都心居住を継続するが、多くの人々が向かうのが、都市郊外の衛星都市だ。
衛星都市で一日を過ごす人が増えれば、衛星都市の平日の姿が変わる。飲食施設も昼間の対応だけでなく夜も含めて多様な姿をみせるようになる。
ただし、店を訪れるのは同じ職場の仲間ではない。ファミリーやカップル、同じ地域の仲間といった客層が対象となる。当然提供するメニューも変わる。居酒屋だけでなく、イタリアンやフレンチ、和食、家庭料理、いろいろなタイプのものになる。
遊び方も変わるだろう。カラオケだけでなく、カウンターバー、ダーツバー、スポーツや映像を売り物にする飲食、いろいろな形態をその日その時の気分に応じて使い分ける、新しい飲食業態が続々誕生する。
遊ぶ、寛ぐ単位が変われば、新しい文化や芸術が誕生する可能性が高まる。音楽や芸術を自ら楽しむ人が増えればそれが新しい地域文化を育むことになる。衛星都市発の文化が生まれるチャンス到来である。日本社会は相当変わるだろう。
牧野 知弘
オラガ総研株式会社 代表取締役 / 不動産事業プロデューサー

1983年東京大学経済学部卒業。
第一勧業銀行(現みずほ銀行)、ボストンコンサルティンググループを経て、1989年三井不動産に入社。不動産買収、開発、証券化業務を手がける。
2009年オフィス・牧野、2015年オラガ総研、2018年全国渡り鳥生活倶楽部を設立、代表取締役に就任。
ホテル・マンション・オフィスなど不動産全般に関する取得・開発・運用・建替え・リニューアルなどのプロデュース業務を行う傍ら、講演活動を展開。
著書に「空き家問題」「不動産激変~コロナが変えた日本社会」(ともに祥伝社新書)、「人が集まる街、逃げる街」(角川新書)、「不動産の未来」(朝日新書)等。文春オンラインでの連載のほか、テレビ、新聞等メディア出演多数。
企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから