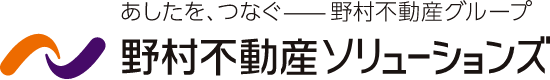CRE戦略
行きたくなるオフィスとは何か?

コロナ禍によるリモートワークの拡大でオフィスの役割があらためて問われる中、「フリーアドレス」などコラボレーション機能に特化したオフィスに注目が集まっている。一方でコラボレーション機能に特化したオフィスでは、イノベーションの創出の起点・企業文化の象徴としての機能を果たすのが難しい。本記事では、従業員の多様な働き方のニーズにこたえ、出社したくなる「フルパッケージ型」オフィスを提案・推奨する。
Ⅰ.台頭するオフィス再定義論への疑問
我が国において、多くの企業がコロナ禍でのBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)として緊急避難的に導入した在宅勤務でのテレワークが、多様な働き方の選択肢の1つとしても活用されつつある中、「出社する意味を問い直し、従業員が出社したくなるようなオフィスを目指すべく、メインオフィス(本社など本拠となる中核的なオフィス)などオフィスの役割・在り方を再定義すべきである」との考え方が広がっている。
その中でも、「従業員が一人でもできる作業は在宅勤務でこなせるため、オフィスは、従業員がコミュニケーションを交わしコラボレーションを実践する場に変えるべき」との意見が多く聞かれる。これは、在宅勤務とオフィスワークの役割・機能を厳格に切り分けようとする、一見もっともらしい考え方だ。この考え方を突き詰めると、固定席など一人で集中できるスペースが撤去される一方、座席を固定せずに共用する「フリーアドレス」や「ホットデスキング(hot-desking)」が導入され、従業員同士の交流を促すオープンな環境に特化したオフィスに行き着き、座席数を入居従業員数より少なくすることができるため、スペース全体は削減されることになるだろう。コロナ後の平時にも週の半分以上を在宅勤務とするなど、一人で集中して業務を行ったりオンライン会議を行ったりする場としての在宅勤務を働き方の中心に据えれば据えるほど、このような傾向は強まるとみられる。
一方、筆者は、「メインオフィスが担うべきイノベーション創出の起点や企業文化の象徴としての機能は、在宅勤務などのテレワークでは代替できず、主として都市部に立地するメインオフィスの重要性は、コロナ前後で何ら変わらない」との主張をコロナ禍の中でいち早く打ち出したが、その中で「アフターコロナの働き方・オフィス戦略の在り方として、企業はメインオフィスをワークプレイスの中核に据える戦略の下で、従業員の働き方の多様なニーズにもできるだけ対応するために、週3日以上の出社(=2日以下のテレワーク)をガイダンスとして推奨することが望ましい」と主張してきた1。
コラボレーション機能に特化したオフィスでは、メインオフィスが本来担うべき、イノベーション創出の起点や企業文化の象徴としての機能を十分に果たせない、と筆者は考える。本稿では、この点について筆者の考え方を紹介するとともに、特化した機能ではなく、あたかも多様性を持った「街」のように、できるだけ多くの機能を装備した「フルパッケージ型」のオフィスを従業員が出社したくなるオフィスとして紹介し推奨したい。
1筆者は、「メインオフィスの重要性は今後も変わらない」との主張を拙稿「今、企業に求められるサテライトオフィス活用~新型コロナウイルスがもたらすワークプレイス変革」日本経済新聞朝刊2020年6月30日にてコロナ禍の中でいち早く打ち出した。その後体系的にまとめた論考としては、拙稿「アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)」ニッセイ基礎研究所『基礎研レポート』2021年3月30日(オリジナル版)、同「アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研REPORT』2021年6月号(概要版)、同「アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研所報』Vol.65(2021年7月)(再構成版)、同「コロナ後のオフィス アマゾン、グーグルが増床計画 引き出したい従業員の創造性」毎日新聞出版『週刊エコノミスト』2021年8月31日号、同「第10章・第1節 ニューノーマル時代における研究所などオフィス戦略の在り方」『研究開発部門の新しい“働き方改革”の進め方』技術情報協会2022年3月を参照されたい。
Ⅱ.イノベーションの源となるアイデアの生成プロセス
ここで、従業員がイノベーションにつながり得るアイデアを生み出すプロセス経路を考えてみよう。まず、メインオフィス内のインフォーマルなコミュニケーションを促す休憩・共用スペースなどで、異なる部門の従業員との何気ない雑談・会話や時には白熱した議論から、これまでにない気付きやインスピレーションを得るのが第一段階(フェーズ1)だ(図表1)。このフェーズ1に入れなければアイデア生成という「回路」のスイッチは入らず、イノベーションの源となり得るアイデアは生まれてこない。その意味では、フェーズ1に偶発的に出会うことが極めて重要だ。
フェーズ2では、得られた気付きやひらめきを、間を置かずに一人で集中して熟成し深掘りすることで、ビジネスに使える具体的なアイデアに一気呵成に落とし込まなければならない。ところが、従業員間の交流を促す機能に特化したオフィスでは、周りが騒がしく集中できないために、気付き・ひらめきを熟成させる集中作業だけのために、わざわざ自宅に帰ったり、サテライトオフィスの個別ブースを予約しなければならなかったりするのであれば、そのようなオフィス環境は本末転倒であり、創造的な環境には程遠いと言わざるを得ない。それでは、気付き・ひらめきを整理されたアイデアに落とし込むタイミングを逸してしまい、ビジネスに活かされない単なる気付き・ひらめきの段階で終わってしまうことになりかねない。
フェーズ3は、生成されたアイデアを文章・図表・数式などに形式知化する最終段階であり、ここでも集中力が必要だ。
 (備考)オフィスの「コラボスペース」とは、従業員間のコミュニケーションやコラボレーションを促進するために設置された休憩・共用スペース等を指す。
(備考)オフィスの「コラボスペース」とは、従業員間のコミュニケーションやコラボレーションを促進するために設置された休憩・共用スペース等を指す。(資料)ニッセイ基礎研究所(筆者)作成。
Ⅲ.「フルパッケージ型」オフィスでアイデア生成プロセスを一気呵成(いっきかせい)に回し切る
前述したように、イノベーションにつながり得るアイデアを生み出すためには、気付きやひらめきの鮮度が高いうちに、間を置かずに一気呵成にアイデアの形式知化までのプロセスを回し切ることが重要であるため、各フェーズは中断・分断せずに同じオフィス内で一気通貫で進めるべきだ(図表1)。
フェーズ2以降の集中作業は、自宅に持ち帰って在宅勤務で行うのではなく、フェーズ1と同じメインオフィス内の固定席や集中ブースで行うことが効率的だ。またフェーズ2では、少人数で深掘りの議論を行うこともあり得るため、少人数で密度の濃いミーティングをじっくり行える分散した小さな部屋も、オフィスに完備されていることが望ましい。
このようにイノベーションの源となるアイデアを効率的に生み出すためには、メインオフィスでは、従業員間の交流を促すオープンな環境と集中できる静かな環境といった両極端にある要素を共存させるなど、多様なスペースの設置が求められる。メインオフィスは、ソロワーク空間としてのテレワークとの役割・機能のすみ分けにより、交流・コラボレーション機能といった単一の機能に集約するのではなく、アイデア生成プロセスのフェーズ毎の作業に対応できるように、できるだけ多くの利用シーンを想定した「フルパッケージの機能」を装備することが望ましい、と筆者は考える。
Ⅳ.行きたくなるオフィスは従業員によって異なる
そもそも「行きたくなるオフィス」と言っても、従業員が望むオフィス環境は、個々の嗜好や性格特性などによって異なるはずだ。また同じ従業員でも、その時々に取り組んでいる業務の内容や気分・体調によっても、働く場に対して異なるニーズを持つことはあり得るだろう。
企業が従業員にその時々のニーズに応じて「働く環境の選択の自由」を与えることは、「働き方改革」の本質だ。従業員の働く環境の多様なニーズにできる限り応えるとの視点からも、コラボレーション機能だけに絞り込むのではなく、メインオフィスには、あたかも多様性を持つ「街」を再現・凝縮したような、「フルパッケージ機能」の装備が望まれる。
利用シーンの異なる多様なスペースを設置する上で、照明の明るさやオフィス家具を変えたり、観葉植物や心地の良い鳥のさえずりの音など自然の要素(バイオフィリックデザイン)を取り入れたりと、内装・設備面での多くの工夫の仕方があり得るだろう。
企業が従業員の働く場の多様なニーズにできるだけ寄り添った対応・サポートを行うことは、従業員の満足度や士気・忠誠心を高めるとともに、働きがい・快適性・心身の健康(ウェルネス)・幸福感(ウェルビーイング)を向上させ、活力・意欲・能力・創造性(クリエイティビティ)を存分に引き出すことを通じて、生産性向上やイノベーション創出につながり得る、と筆者は考える。
オフィスは従業員にとって、各々の能力や創造性を最大限に活かすことができる場所であり、そのコミュニティに属していることを誇りに感じることができる場所でなければならない。自席などアイデンティティを持てる居場所も必要だ。多様性のない機能特化型のオフィスでは、「居場所がない」「愛着や誇りを持てない」と感じる従業員が多くなってしまうのではないだろうか。メインオフィスは、多くの従業員が愛着や誇り(エンゲージメント)を持てる場でなければ、そこで企業文化を醸成することはできず、会社への帰属意識を高めることもできない。
Ⅴ.おわりに~「フルパッケージ型」オフィスのすすめ
台頭するオフィス再定義論で強調される「従業員間の交流を促す機能」は、イノベーションを起こすための「アイデア生成回路」の非常に重要なスイッチとして、メインオフィスに勿論欠かせないものだが、メインオフィスがその機能だけに特化してしまうと、逆にイノベーションを起こしにくくなったり、また企業文化や会社への帰属意識も醸成しにくくなったりするのではないか、と本稿で疑問を投げかけた。イノベーション創出の起点と企業文化の象徴として従業員の帰属意識を高める場は、いずれもメインオフィスが本来担うべき最も重要な機能だ。
このことは、従業員が出社したくなるようなオフィスを考えた場合、それを従業員間の交流促進といった単一の機能だけで形成することが難しいことを示唆している。訪れると誰もがワクワクできる多様性・利便性に富んだ街・都市をモチーフとした設計デザインの下で、様々な利用シーンを想定してできるだけ多様なスペースを取り入れた「フルパッケージ型」のオフィスこそが、コロナ後のメインオフィスの在り方にふさわしい、と筆者は考える。
アフターコロナの在り方として、従業員間の交流はオフィス、一人で集中するなどのソロワークは在宅勤務というように、オフィスワークと在宅勤務の役割・機能をわざわざ厳格に切り分けたり、分断したりする必要はない、と筆者は考えている。人間は本来、リアルな場に集い直接のコミュニケーションを交わしながら信頼関係を醸成し、協働して画期的なアイデアやイノベーションを生むことで社会を豊かにしてきた。このことは、変えようとしても変わらない「人間の本性に根差した人間社会本来の在り方」だ。多様な働き方の選択肢の1つでありBCPの有力な手段でもある、在宅勤務でのテレワークは勿論今後も積極的に活用すべきだが、それだけではイノベーション創出は完結しないし、企業文化や帰属意識を醸成することもできない。アイデアの生成プロセスのように、同じオフィス内にて一気通貫で進めた方が効率的である業務については、在宅勤務とオフィスワークでわざわざ工程を分断すべきではない。コロナ後は、これまでリアルな場でコミュニケーションを交わしコラボレーションをしてきた人間の本性に逆らうべきではないだろう。
行きたくなるオフィスを考えるなら、筆者が提唱する「フルパッケージ型オフィス」の考え方を是非取り入れてみてはいかがだろうか。「街や都市をモチーフとした設計デザインの下で、様々な利用シーンを想定して多様なスペースを取り入れること」は、従業員の創造性を企業競争力の源泉と認識し、それを最大限に引き出しイノベーション創出につなげていくための創造的なオフィス(クリエイティブオフィス)の「原理原則」であり、コロナ前後で変わるようなものではない、と筆者は考えている。このクリエイティブオフィスの在り方・原理原則は、筆者が先進事例の共通点から抽出したものであり、「クリエイティブオフィスの基本モデル」2と呼んでいる(図表2)。このクリエイティブオフィスの基本モデルも、今後のオフィスづくりに是非活かしていただきたい。
「企業が事業継続のために使う不動産を重要な経営資源の一つに位置付け、その活用、管理、取引(取得、売却、賃貸借)に際し、CSR(企業の社会的責任)を踏まえた上で最適な選択を行い、結果として企業価値最大化に資する経営戦略」を「CRE(企業不動産)戦略」3と呼ぶが、クリエイティブオフィスの構築・運用も、このCRE戦略の下で組織的に取り組まなければならない。多くの日本企業の在り方としては、導入・実践が遅れているとみられる大本のCRE戦略をしっかりと取り入れた上で、それに基づく創造的なオフィス戦略を新たに構築することが急務だろう。
 (備考)「健康経営」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標。
(備考)「健康経営」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標。(資料)百嶋徹「第7章・第1節イノベーション促進のためのオフィス戦略」『研究開発体制の再編とイノベーションを生む研究所の作り方』技術情報協会2017年10月
2クリエイティブオフィスの基本モデルについては、拙稿「クリエイティブオフィスのすすめ」ニッセイ基礎研究所『ニッセイ基礎研所報』Vol.62(2018年6月)、同「第7章・第1節イノベーション促進のためのオフィス戦略」『研究開発体制の再編とイノベーションを生む研究所の作り方』技術情報協会2017年10月、同「クリエイティブオフィスの時代へ」ニッセイ基礎研究所『研究員の眼』2016年3月8日、同「イノベーション促進のためのオフィス戦略」『ニッセイ基礎研REPORT』2011年8月号を参照されたい。
3先進的なグローバル企業のCRE戦略には、①創造的なワークプレイスの重視に加え、②CREマネジメントの一元化(専門部署設置による意思決定の一元化とIT活用による不動産情報の一元管理)、③外部ベンダーの戦略的活用、という3つの共通点が見られ、筆者は、これらをCRE戦略を実践するための「三種の神器」と呼んでいる。
百嶋 徹(ひゃくしま とおる)
株式会社ニッセイ基礎研究所 社会研究部 上席研究員
1985年野村総合研究所入社、証券アナリスト業務、財務・事業戦略提言業務に従事。野村アセットマネジメント出向を経て、98年ニッセイ基礎研究所入社。 企業経営を中心に、産業競争力、イノベーション、AI・IoT・自動運転、スマートシティ、CRE(企業不動産)・オフィス戦略、CSR・ESG経営等が専門の研究テーマ。 日経金融新聞(現・日経ヴェリタス)およびInstitutional Investor誌のアナリストランキングで素材産業部門第1位(1994年)。明治大学経営学部特別招聘教授を歴任(2014~16年度)。2006年度国土交通省CRE研究会の事務局をPJマネージャーとして担当。国土交通省CRE研究会ワーキンググループ委員として『CRE戦略実践のためのガイドライン』の作成に参画、「事例編」の執筆を担当(2008~10年)。国土交通省『企業による不動産の利活用ハンドブック』の発刊に寄せて、論考「地域活性化に向けた不動産の利活用」を寄稿(2019年)。CRE戦略の重要性をいち早く主張し、普及啓発に努める。
企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから