トレンド
あの跡地はどうなっている? 日本の万博遺跡めぐり(前編)

大阪・関西万博が開幕した。チケットを購入して、どのパビリオンを見ようか、どの催しに参加しようか、ワクワクしながら考えている向きも多いことだろう。
万国博覧会と名前が付く催しを遡れば、水晶宮と呼ばれる鉄とガラスの大建築が建てられた、第1回ロンドン万博(1851年)や、エッフェル塔が建てられた第4回パリ万博(1889年)など、19世紀から各国でそれぞれに開催されてきた。しかし、1928年に国際博覧会条約が締結されてからは、パリに本部を置く博覧会国際事務局の承認を受けて開催されるようになった。テーマ設定の範囲や、パビリオンの建設を開催国側が行うか出展国側が行うかなどにより、一般博と特別博に分かれる。現在は規模が大きい登録博と、テーマを絞った認定博の2分類に変わっており、今回の大阪・関西万博は登録博にあたる。
日本では過去に5回の万博が催され、その会場ではそれぞれの時代を代表する建築家たちが意欲的なデザインのパビリオンを設計してきた。20年ぶりの万博開催となるこの機会に、これまで行われた日本開催の国際博覧会を振り返り、その跡地が今、どのようになっているか、万博で建てられた建物がどれくらい残っているかを見ておこう。記事は2回分かれる。前編では1970年の大阪万博、1975年の沖縄海洋博、1985年のつくば科学博を取り上げる。
Ⅰ.森へと還った未来都市 大阪万博/1970年
まずは、1970年の大阪万博。正式名称は日本万国博覧会である。アジアで初めて開催された万博で、テーマは「人類の進歩と調和」。大阪府吹田市の丘陵を切り開いた敷地には、先進的な構造や工法を採ったパビリオン群が立ち並んだ。それらを動く歩道が結んだ万博会場は、未来都市を先取りしたものとも評された。そこに3月15日から9月13日までの期間中、のべ6421万人が押し寄せる。これは2010年の上海万博に抜かれるまで、万博史上最高の来場者数だった。
その会場は今、万博記念公園となっている。大阪モノレールの万博記念公園駅を降りると、目の前のエリアにはショッピングアーケード、シネマコンプレックス、水族館と動物園の複合施設などがある。ここは元々、エキスポランドという遊園地があったところ。その脇には万博協会本部だった建物(万博記念ビル)が、今も残っている。
 万博記念ビル(旧万博協会本部ビル、設計:根津耕一郎)
万博記念ビル(旧万博協会本部ビル、設計:根津耕一郎) 太陽の塔(設計:岡本太郎+集団制作建築事務所)
太陽の塔(設計:岡本太郎+集団制作建築事務所)ブリッジを渡って、府道大阪中央環状線を挟んだ反対側へ。中央口の公園ゲートから入ると、目の前に太陽の塔がそびえる。これは大阪万博のテーマ館として建てられたものだ。芸術家の岡本太郎がデザインした古代の呪物を想起させる太陽の塔は、未来都市のような会場で異物感が強かったはず。これが大阪万博のシンボルとして広く認められ、万博後も長く残されることになったのは想定外の結果かもしれない。内部は長らく非公開だったが、塔の耐震工事と合わせて内部展示の再生復元も実施し、2018年3月から公開している。
太陽の塔の周りには、丹下健三が設計したお祭り広場の大屋根があった。これは1978年に解体されてしまったが、スペースフレームのごく一部がイベント広場の一角に残されている。在りし日の巨大構造物のスケールを、そこから想像することができる。
太陽の塔の東側にあるEXPO'70パビリオンは、大阪万博の鉄鋼館だった建物。万博後も使用される恒久施設として、前川國男の設計により建てられたが、使用されないまま放置。2010年になってようやく再オープンし、大阪万博の資料を展示する施設として生まれ変わった。会場模型やコンパニオンの制服など、貴重なものが目白押し。鉄鋼館当時のスペース・シアターも残り、ガラス越しに鑑賞することができる。隣接して、2023年に別館もオープンしており、こちらでは太陽の塔についていたオリジナル「黄金の顔」を間近に拝むことができる。
 パビリオン記念碑
パビリオン記念碑一方、北側にある国立民族学博物館は1977年にオープン。大阪万博のテーマ展示として集められた品々がもとになって開設された施設で、その意味ではこれも万博の遺産である。建物の設計は、大阪万博のテーマ館カプセル、タカラビューティリオン、東芝IHI館を手がけて注目された、黒川紀章が担当している。
その向かいにある大阪日本民芸館は、大阪万博で日本民芸館として建てられたもの。万博から用途も変わらず使われ続けている、ただ一つの建物となっている。
アートワークも残っている。「夢の池」にある彫刻は、いずれもイサム・ノグチによるもの。万博の時にはジェットノズルから勢いよく水を噴出していたが、その機能は失われてしまった。
ここまで公園内にある万博関連の建物を紹介してきたが、敷地のほとんどは緑で覆われている。特に公園の西側半分は、うっそうと木が茂る森だ。パビリオンを撤去した跡に樹木を人工的に植えることで、万博会場は多様な動植物が生育する自然環境へと変わった。
歩いていると、ところどころで地面に石の銘板が埋められているのを眼にする。記されているのは、博覧会開催時にそこにあったパビリオンの名前。これがあるのでかろうじて、あのアメリカ館やソ連館が立っていたと信じられるが、そうでなかったら、よもやここがあの万博会場だったとは思わないだろう。未来都市は、森へと還っていったのだった。
Ⅱ.海上都市の形は子どもたちの遊具に 沖縄海洋博/1975年
大阪万博のわずか5年後に催されたのが沖縄海洋博、正式名称は沖縄国際海洋博覧会である。「海ーその望ましい未来」をテーマとした、特別博として開催された。本土復帰を果たして間もない沖縄の振興整備を進める狙いも込められたイベントだった。
会場は沖縄本島北部に位置する本部町。海に面した細長い敷地は、現在、海洋博公園となっている。園内には植物園の熱帯ドリームセンター、沖縄の民家を移築したおきなわ郷土村などがあり、平日も観光客で賑わう。
その中の一つ、海洋文化館はカヌーのコレクションなど、海洋文化にまつわる民族資料を展示する施設。海洋博の時に建設されたもので、改修を経ながら現在まで存続している。
 旧水族館(設計:槇文彦)の一部を再生した休憩施設
旧水族館(設計:槇文彦)の一部を再生した休憩施設海洋博公園で一番の人気施設は、ジンベエザメやマンタが泳ぐ大水槽を目玉とする沖縄美ら海水族館だ。この施設は、海洋博の時に建設され、会期後も営業を続けていた水族館を、継承発展させて2002年にオープンしたもの。槇文彦が設計した旧水族館の建物は建て替えで失われたが、その構造体の一部を再生し、休憩施設として活用している。プレキャスト・コンクリートを組み合わせた空間は独自のもの。プリツカー賞を受賞した世界的な建築家の作品だけに、部分とはいえ味わえるのはうれしい。
海洋博のテーマ館として日本政府が出展したのは、海に浮かぶアクアポリスだった。未来の海上都市を体験できる実験施設として、建築家の菊竹清訓が設計。建造地の広島から3隻の船で沖縄まで曳航され、会場の陸地と桟橋でつながれた。80m四方の屋上デッキの下にホール空間を収めた構造物は、会期終了後に県へ引き下げられ、観光施設として使われていたが、老朽化が進んで1993年に閉館。那覇港へ移してレストランにする案も出たが、実現には至らない。2000年には、スクラップ処分が決まり、解体が行われる中国へ向け、再び海を渡って沖縄から消えた。
アクアポリスが接岸していたあたりには現在、アクアタウンと名付けられている遊具施設がある。遊んでいる子どもたちも遊ばせている親たちも意識していないだろうが、その形は明らかにアクアポリスを縮小して模したもの。海洋博の記憶が、世代を超えて受け継がれていくきっかけになるのだろうか。興味深いところだ。
 アクアタウン(夕陽の広場内にある遊具施設)
アクアタウン(夕陽の広場内にある遊具施設)Ⅲ.公園に立つ縮小されたモニュメント つくば科学博/1985年
 科学万博記念公園のモニュメント「科学の門」(元となったテーマ館は設計:日建設計)
科学万博記念公園のモニュメント「科学の門」(元となったテーマ館は設計:日建設計)10年ぶりに日本で実現した国際博覧会がつくば科学博、正式名称は「国際科学技術博覧会」である。「人間・居住・環境と科学技術」をテーマとした、特別博として開催された。
会場に選ばれたのは、東京への一極集中を解消するために計画された、つくば研究学園都市。まだまだ開発の途上であり、省庁や研究機関の移転が遅れるなかで、これを推し進めるための博覧会だった。つくばエキスプレスが開通するのは、その20年後となる。
科学博の会場内に建てられた各パビリオンでは、映像やロボットの最新技術を競い合った。特に話題を呼んだのがソニーのジャンボトロンで、14階建てビルの高さに相当する、世界最大の映像ディスプレイだった。
ジャンボトロンが立っていた周辺は、現在、科学万博記念公園になっている。芝生が広がり、子供を連れた家族が憩いのひとときを味わっている。公園の入口に立っているのは、科学博の政府出展テーマ館を一部復元したモニュメントだ。元になったのは、約41mの高さを持つガラス張りのシンボルタワーで、4本の柱がそれぞれエレベーターを収め、展望室を支えていた。
 筑波西部工業団地に立つ電柱(設計:黒川紀章)
筑波西部工業団地に立つ電柱(設計:黒川紀章)会場跡地の北側エリアは筑波西部工業団地に替わり、企業の研究施設や巨大な物流施設が立ち並んでいる。科学博当時の建物は残っていないが、道路の脇に並ぶ電柱は科学博の頃からあるもので、黒川紀章が設計している。
メイン会場から離れた、現在のつくば駅から近いところには第2会場があった。ここには当時、世界最大と言われた直径25.6mのプラネタリウムを擁するつくばエキスポセンターが建てられた。博覧会後も使用する恒久施設として計画されたもので、現在も科学技術について展示するサイエンスミュージアムとして運営されている。科学博の資料や関連グッズを展示したメモリアルコーナーもあり。
その向かい側、池の中に浮かぶようにして立つ建物は、科学博の時にレストハウスとして設けられた建物で、現在はつくば市民ギャラリーとして活用されている。
つくば市には科学博でつくられてそのまま遺っているものは少ないが、研究学園都市としてデザインされた街の各所に、ほんのりとした万博らしさを嗅ぎ取ることもできる。都市自体が、万博遺産とも言えそうだ。
以上、前編では3つの万博跡地を回った。後編では1990年の大阪花博と2005年の愛・地球博を取り上げる。
磯 達雄(いそ たつお)
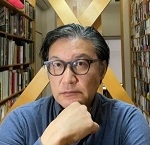
埼玉県東松山市生まれ。名古屋大学工学部建築学科卒。オフィス・ブンガ共同主宰。桑沢デザイン研究所、武蔵野美術大学、早稲田大学芸術学校非常勤講師。日経BP社『日経アーキテクチュア』編集部を経て、2000年に独立。建築ジャーナリストとして、建築専門誌や一般誌に建築の記事を執筆する。著書に『昭和モダン建築巡礼西日本編』『昭和モダン建築巡礼東日本編』『ポストモダン建築巡礼』(宮沢洋との共著、日経BP社)、『ぼくらが夢見た未来都市』(五十嵐太郎との共著、PHP研究所)、『日本のブルータリズム』(山田新治郎との共著、トゥーヴァージンズ)など。
企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから










