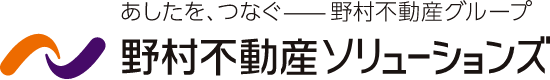トレンド
【連載】2030年の東京不動産(第1回)
~2030年の社会とオフィス、住宅のあり方~

2013年以降活況を呈してきた東京の不動産。20年の2月から世界を席巻したコロナ禍は、日本の経済や社会に大きな影響をもたらしたが、いっぽうでコロナ禍がきっかけになり、人々の生活は大きく変化した。そうした社会の変化に対し、東京の不動産はどのような変化をみせていくのか、本稿では現在から8年後の2030年を見据えた東京の不動産について考えてみよう。
第1回の今回は2030年における日本社会の変化だ。変化ははじめ小さな針でつついたような穴で、誰もその穴の存在に気づかないものだ。ところがある日改めて目にすると、ちょっと目立つ穴になる、そしてその穴はやがて修復が難しいような大きな穴へと拡大する。
2030年の未来と不動産について展望してみよう。
Ⅰ-Ⅰ.コロナ禍によって変わる社会、変わらぬ社会
不動産は人々が生活するための社会的なインフラである。したがって今後の東京において多くの人々を支える社会インフラとしての不動産がどのように変化するかを考えるには、これからの社会、ライフスタイルがどう変遷するかを予測することが極めて重要である。
まずはコロナ禍が生じたことによって社会や人々のライフスタイルに及ぼした影響を、①コロナ禍という感染症の蔓延による一時的な事象と捉えることができるものと、②コロナ禍はあくまでも変化のためのきっかけにすぎず、時代の変化や流れがコロナ禍によって加速された、つまりこの変化が今後の生活の中で日常となる、新たな社会常識になる、というものとを明確に識別することにある。
ライフスタイルが変化するかどうかということは、現代の社会生活において勤労するということの定義、つまり「働き方」がどう変化するかを見極めることだ。コロナ禍において多くのワーカーがテレワークという就業形態を余儀なくされた。
このテレワークが今後も継続する新しい働き方になるか、この働き方はあくまでも緊急避難的なもので、アフターコロナの世界においては再びワーカーは自宅からオフィスへ通勤する日常に戻るかについては様々な議論がある。
2030年においてもコロナ禍が猛威を奮っているとは考え難い。したがって2030年の働き方は緊急避難的なテレワークではなく、日常の働き方としてテレワークを選択する企業やワーカーがどの程度いるのか、ということに帰結する。
この論点について明確であるのは、人々のライフスタイルが、コロナ前の日常に「完全に」戻ることはないということだ。人類の歴史を顧みれば、人々の働き方は時代によって変遷している。いうまでもなく、縄文時代は狩猟をすることが働き方であった。弥生時代には農耕が主体となり、やがて生産物を物々交換することで街が形成され、商業が発達する。産業革命後は、工場生産が始まり多くのワーカーは自宅から工場という生産現場に通い、工場労働者として糧を得ていく。
Ⅰ-Ⅱ.事務系サラリーマンの働き方が変わる
現代のような事務系サラリーマンとしてオフィスに通勤する働き方が主流となったのは、実は戦後の傾向である。今では自営業者の数は減少し、労働者の8割以上が何らかの企業に所属し、職場である事務所や工場などに「通勤」をするというサラリーマンになっている。
そして今でも事務系ワーカーの多くが、生産現場に様々な指示、命令や企業管理を行うためにオフィスに出社して働くという形態をとっている。その結果として東京にはオフィスワーカーの受け皿としてのオフィスビルが数多く建設されてきている。東京都心部では、現在でも多くの再開発事業においてオフィスを中心とした開発を掲げているのも、こうしたライフスタイルが今後も継続されるという前提のもとであることは言うまでもない。
だがいっぽうで、コロナ禍は多くのワーカーにとって「通勤から解放される」という思わぬ副次的な体験をもたらすことになった。
これまでは自宅からオフィスに通勤するということは働くという行為の前提条件であり、誰しもが疑うことのない基本行動だった。オフィスにおいては大勢のワーカーが一同に集まり、机を並べ、ルーティンワークをこなし、ミーティングを行う。仕事の指示、命令は主に口頭で行われ、チームワークを重視し、共通の目的を設定し、目標達成に向けて進む軍隊のような働き方だった。
ところがテレワークの実施によって、全員がオフィスというハコに集まって働く必要が必ずしもないことに気づくきっかけとなったと言える。
もちろん業種や職種によっては従来通りの働き方が必須であることも判明することになったが、これからの働き方では、それぞれのワーカーが自らの能力を持ち寄ってタスクチームとして働くものに移行していくことが想像される。いわゆるJOB型の働き方を志向するワーカーが現在よりも格段に増えることが予想されるのだ。
ルーティンワークの多くがAIなどのテクノロジーに代替されることで、オフィスを主戦場とした働き方はあまり重要ではないものとなってくることが予想される。
未来のオフィスは、家やコワーキング施設ではなかなか実現できない仕事をやる場としての空間になる。製品開発などで実験を行う、家には設置できない器具、空調、排水などの特殊設備を備えている、その場で五感を使って確かめるような場としての機能が求められる。
日々の仕事の中で自宅ではできない作業や集中しての仕事などは、自宅のあるエリア内にあるコワーキングスペースで働き、都心にあるようなオフィスは高度な機能を備えたかなり専門分野に特化した設えへと進化していく。そしてそれらの機能は、限りなくシェアされ、その場を使用する企業やワーカーは賃料ではなく、使用料を支払って利用する形態に変わっていくだろう。

Ⅰ-Ⅲ.働き方の変化は住まいの在り方にも影響を与える
働き方の変化は住宅にも影響が及ぶ。通勤を前提にしないのであれば、無理に都心に住む必要はなく、自分の趣味嗜好にこだわった住宅を選ぶ傾向が強くなる。都心と郊外、あるいは地方との二拠点居住や季節や自分の都合に合わせて住む場所を変えていく多拠点居住といったライフスタイルも根付いていくだろう。
一日の多くを自分が住む家やマンション、そして生活基盤である自分が住む街の中で過ごすことになると、自分が住む街や住宅に対する見方が大きく変わる可能性がある。これまでの住宅は、都心に通勤することが前提だった。相変わらず、都心への通勤を前提に住宅を選ばざるを得ない仕事の人たちも存在するだろうが、大企業や専門的な知見で仕事を行うプロフェッショナルを中心に、街での日々の生活そのものを楽しむ傾向が高まるだろう。彼らは自分の暮らす街で仕事をしながら、夕方からあるいは休日に都心のエンターテインメント施設で遊ぶようなライフスタイルになる。
Ⅰ-Ⅳ.東京の不動産が変わる
働き方の変化を背景とした、時代の急速な変化で東京の不動産はどういった姿に変貌するだろうか。
まず高齢化社会が自明であることを考えるならば、相続対策を目的とする不動産投資はさらに活況を呈するだろう。ただ気を付けなければならないのは、マンションなどの投資用不動産を利用する借手、テナント需要がどこまで確保できるかになる。
オフィス機能が縮小に向かう中で、テナント需要を確保するには、立地がこれまで以上に重要となる。二拠点居住の進展は不動産流通マーケットの活性化につながるが、都内でも街やエリアによる格差は鮮明になるのが2030年の東京だ。コロナ禍後に確実に復活するだろうインバウンドの動向、外国人居住者の増加も需要を見極めるための重要なポイントとなる。
東京はこれまでのオフィス中心の街から、オフィスに加え、文化や芸術関連の施設も含めたコンプレックス型のエンターテインメントの街に変貌していくだろう。そうした変化の中で東京の不動産はさらに活況を呈していくことになる。時代の変化は東京という街の姿を大いに変える可能性があるのだ。
働き方が変わることで、オフィスや住宅といった不動産の根幹となる用途に大きな変化が生まれそうなのが2030年の東京不動産なのである。
次回は、ライフスタイルの変化が商業施設やホテルのあり方にどのような影響を与えるかについて考察する。
牧野 知弘
オラガ総研株式会社 代表取締役 / 不動産事業プロデューサー

1983年東京大学経済学部卒業。
第一勧業銀行(現みずほ銀行)、ボストンコンサルティンググループを経て、1989年三井不動産に入社。不動産買収、開発、証券化業務を手がける。
2009年オフィス・牧野、2015年オラガ総研、2018年全国渡り鳥生活倶楽部を設立、代表取締役に就任。
ホテル・マンション・オフィスなど不動産全般に関する取得・開発・運用・建替え・リニューアルなどのプロデュース業務を行う傍ら、講演活動を展開。
著書に「空き家問題」「不動産激変~コロナが変えた日本社会」(ともに祥伝社新書)、「人が集まる街、逃げる街」(角川新書)、「不動産の未来」(朝日新書)等。文春オンラインでの連載のほか、テレビ、新聞等メディア出演多数。
企業不動産に関するお悩み・ご相談はこちらから