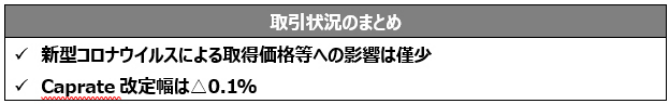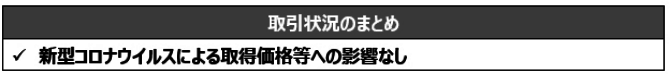日本の法人の99.7%は中小企業で、その大半は同族会社です。時代が変わっても同族会社の経営者の多くは親族内承継を望んでおり、安定した経営を継続していくためには、自社株式や会社に賃貸している不動産などの事業用資産を後継者に集中して承継させる必要があります。今回は、自社株式等の承継方法の一つである、贈与の課税方法を確認していきます。
1.「生前贈与」で自社株式を承継
株主総会で重要事項を決定するためには、2/3以上の議決権が必要になります。これは後継者が承継する自社株式の目安になりますが、かなり高い割合です。しかも同族会社の場合、過去に経営者が会社に自己資金を投入した結果、経営者の相続財産のうちに占める自社株式や事業用資産の割合が高く、これらを後継者に集中して承継させようとすると、多額の買い取り資金や、相続税の納税資金が必要になる可能性があるため、十分な事前対策が必要なのです。
後継者に自己株式等を承継していく方法としてまず考えられるのが、生前贈与と遺言の活用です。いずれも後継者以外の相続人の遺留分や心情に配慮する必要がありますが、後継者へ集中して財産を承継させる方法として有効です。特に生前贈与は、自社株式の評価の低い時などタイミングや回数を選んで移転できるメリットがありますし、贈与後は遺言のように自由に撤回することができませんので、譲り受けた後継者の地位は安定します。デメリットとしては、一般に贈与税の方が相続税より税負担が重い点です。
生前贈与の課税方法としては、まず「暦年課税」と、「相続時精算課税」があります。この他、要件を満たせば、自社株式の承継に係る納税猶予制度という選択もあります。
2.「暦年課税」の活用
暦年課税では、110万円の基礎控除内で子や孫などに広く時間をかけて贈与をし、相続対策をしている方も多いと思いますが、財産の総額が多いと時間がかか りすぎて効果がなかなか見込めません。このような場合には、あまり基礎控除の枠にこだわらず、例えば300万円や500万円といったまとまった額を贈与した方が効果的です。ちなみに贈与税額は300万円で19万円(実効税率6.3%)、500万円で53万円(同10.6%)になります。相続税より低い実効税率で贈与するのであれば、その税率の差で生じる金額相当分が節税できますので、必ずしも贈与が不利とはなりません。
3.「相続時精算課税」の適用は慎重に
相続時精算課税は、対象が65歳(平成27年以降60歳)以上の親から20歳以上の子(平成27年以降は孫も含む)への贈与に限られます。この制度は贈与者ごとに選択でき、例えば父からの贈与は相続時精算課税とし、母からの贈与は暦年課税とすることも可能です。ただし一度相続時精算課税を適用すると、その贈与者からの贈与は継続して相続時精算課税となり、暦年課税に変更することはできませんので、将来を見据えた適用が必要です。
この制度は、贈与時の負担を軽減すべく複数年に渡り利用できる2,500万円までの特別控除がありますので、大型贈与に向いているといえます。とはいえ贈与時には課税を繰り延べているだけで、その贈与者が亡くなった時には、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を納めることになります。この時、贈与時の評価額で加算されますので、例えば自社株式を贈与した場合、相続時までに価値が上昇すれば有利になり、反対に価値が下落すれば不利になります。また、配当や家賃のように収益を生む資産を贈与すると、相続財産に加算されるのは贈与した財産本体だけで、そこから生まれる収益は贈与時以降受贈者のものとなります。一方、現金の贈与は、景気によるインフレやデフレを除けば価値の変動がなく、そのままでは収益を生まない資産ですので、相続税の節税効果はありません。相続時精算課税は対象資産を十分に検討しましょう。
ご相談・お問合せ
WEBから
マーケットレポート