「ワンルームマンション投資はやめとけ」―ネットでよく見るこの言葉に、不安を感じたことはありませんか?
成功している人もいる一方で、失敗するリスクや後悔するケースも存在します。
この記事では、ワンルームマンション投資の仕組みから、失敗しやすい落とし穴、成功している人の共通点までを初心者にもわかりやすく解説します。
なお、ノムコム・プロに会員登録いただくと、不動産投資に役立つ情報や最新の物件情報をいち早く確認できるなどの「4つの特典」を無料で受け取ることができます。不動産投資にご興味のある方は、下記リンクからお気軽にご登録ください。
目次
そもそもワンルームマンション投資とは?基本をやさしく解説

ワンルームマンション投資は、不動産投資のなかでも始めやすいとされ、多くの人がチャレンジしています。とはいえ、そもそもどんな仕組みなのか、どういった人が始めているのか 気になる人もいるのではないでしょうか。はじめに、ワンルームマンション投資の基本と実際の投資家像について解説します。
● ワンルームマンション投資の仕組み
● どんな人が始めているのか
ワンルームマンション投資の仕組み
ワンルームマンション投資とは、マンションの1室(主に1Kや1R)を購入し、それを他人に貸して家賃収入を得る投資方法です。
物件は区分所有の形になるため、一棟買いに比べて初期費用が抑えられ、サラリーマンなど一般の人でも始めやすいのが特徴です。
投資家自身が入居者募集や賃貸契約、賃料等の入出金をはじめとする賃貸管理を行うこともありますが、多くの場合は専門業者に委託しています。賃貸管理を委託する場合は管理手数料が発生する点や、建物管理会社に対しても毎月、管理費や修繕積立金といった経費がかかる点に理解が必要です。
この投資は、家賃保証契約(サブリース契約)ではなく集金代行契約の場合だと入居者がいれば安定した収益が期待できる一方で、空室になると収入がゼロになるリスクもあります。
そのため、利回りだけでなく、立地や周辺需要をしっかり見極めて判断することが重要です。
どんな人が始めているのか
ワンルームマンション投資は、主に安定した収入がある会社員や公務員などの人が多く取り組んでいます。金融機関の融資を活用しやすいため、年収がある程度あるサラリーマン層に人気があります。
始める目的は人それぞれですが、「将来の年金代わり」「節税対策」「副収入確保」「保険」などが多く見られます。また、不労所得を得たいという理由で、投資初心者がチャレンジするケースも珍しくありません。
ただし、リスクを正しく理解しないまま始めると、思ったような効果が得られないこともあるため、情報収集が欠かせません。
なぜ「ワンルームマンション投資はやめとけ」と言われるのか
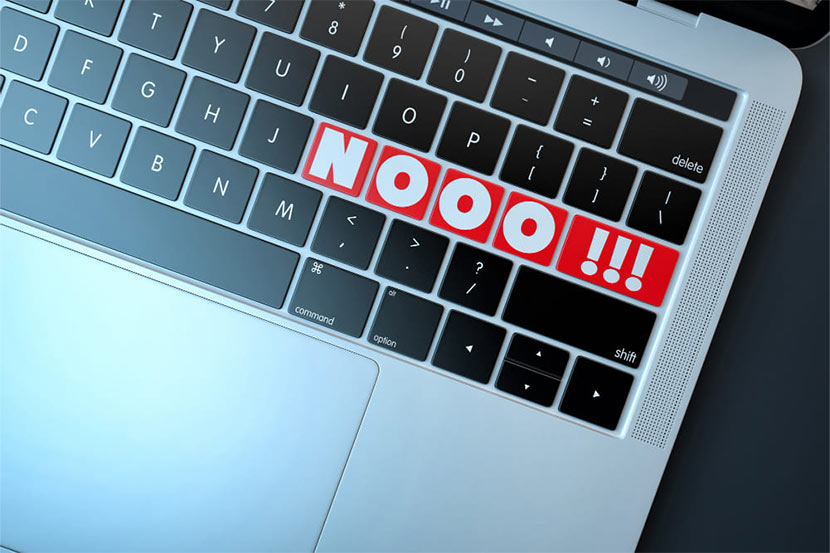
インターネットや書籍で「ワンルーム投資はやめとけ」といった言葉を目にしたことがある人もいるでしょう。実際に挑戦する前にこの言葉の意味を知っておくことは、とても大切です。ここでは、なぜワンルームマンション投資に否定的な意見があるのか、その主な理由を4つに分けて解説します。
1. 収益性が低い
2. 空室や家賃下落などのリスクが高い
3. 節税や年金対策になりにくい
4. 売却が難しく出口戦略が立てにくい
理由1.収益性が低い
ワンルームマンション投資は、手軽に始められる一方で、利回りが低くなる傾向があります。特に都心部の新築物件では、表面利回りが3〜5%ほどしかないことも珍しくありません。そこから管理費や修繕積立金、ローン返済、固定資産税などのコストを差し引くと、実質的な収益はかなり少なくなります。
また、空室が長引く等で家賃を下げざるを得ない場合は、さらに利回りが下がります。その結果、「買ってから手元に残るお金がほとんどない」という事態になることもあります。それどころかマイナスになってでも売却をせざるを得ない状況にもなりかねません。
利回りの数字だけで判断せず、収支のバランスや将来的な支出も踏まえた計画を立てることが必要です。
理由2.空室や家賃下落などのリスクが高い
ワンルームマンション投資では、入居者がいなければ家賃収入はゼロになります。この「空室リスク」は、収益を安定させるうえで最大の課題です。
さらに、築年数が経つと物件の魅力が下がり、家賃を下げないと入居が決まりにくくなることもあります。例えば、新築のときは高い家賃で貸せたとしても、10年後には1〜2万円下がっているケースも珍しくありません。
エリア選びや物件管理の工夫でリスクを下げることは可能ですが、完全になくすことはできないため、空室期間の収支計画もあらかじめ考えておく必要があります。
理由3.節税や年金対策になりにくい

ワンルームマンション投資は、節税や将来の年金代わりを目的に始める人も多いですが、必ずしも思ったような効果が得られるとは限りません。
例えば、節税のために中古物件を購入するケースを考えてみましょう。中古物件は償却期間が短いので短期的に節税効果を得られる側面もありますが、売却となった際には建物の価値が大きく償却されてしまうこともよくあります。その結果、譲渡税が新築物件に比べて大きくなってしまい、思った利益を確保できないといったことも起こり得ます。
また、節税を重視しすぎると、収益性の低い物件を選んでしまい、結果的に損をすることもあります。
年金代わりに家賃収入を得ようと思っていても、家賃下落や空室リスクで毎月の収入が安定しないことも多いため、安易な期待は禁物です。
理由4.売却が難しく出口戦略が立てにくい
投資用ワンルームマンションは、売却益を得るのが難しいという特徴があります。特に新築物件は購入時点で価格が高めに設定されており、中古として売り出す際には大きく値下がりしてしまうことが一般的です。
加えて、物件の立地や築年数、賃貸状況などによっては、なかなか買い手が見つからず、長期間売却できないこともあります。
さらに、売却時には仲介手数料や譲渡所得税などのコストもかかるため、「売ってもほとんどお金が残らなかった」となる可能性もあります。
このように、投資の出口まで見通した計画を立てておかないと、後々の資産運用に大きな影響を与えることになるのです。
実際にワンルームマンション投資で失敗した人のパターンと原因
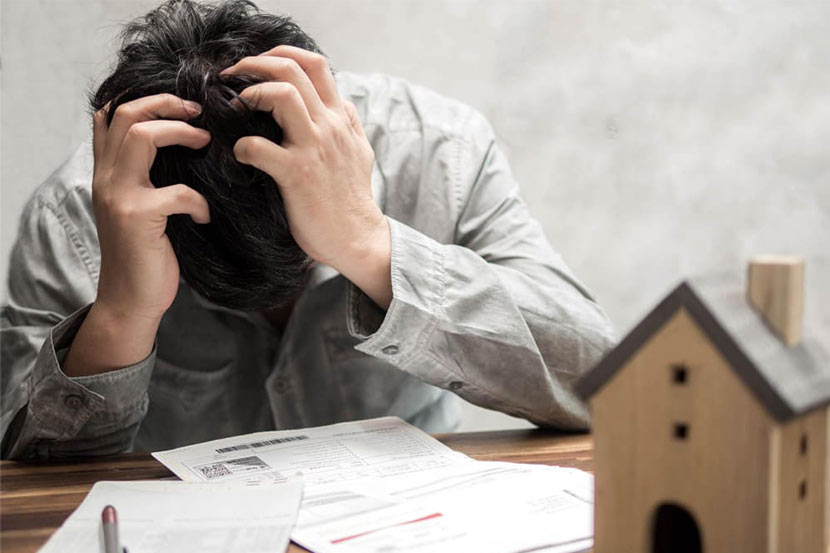
ワンルームマンション投資は、成功すれば安定収入を得られる一方で、現実には失敗して後悔する人も少なくありません。ここでは、実際にワンルームマンション投資でつまずいた人たちの「よくある失敗パターン」を3つ紹介します。
1. 物件選びを間違えたケース
2. 知識がないまま不動産業者に任せたケース
3. 「サブリース=安心」と勘違いしたケース
どれも他人事ではないリアルな話ばかりです。これらの失敗から学び、同じ過ちを繰り返さないためのヒントを見つけましょう。
物件選びを間違えたケース
ワンルームマンション投資でよくある失敗が、「利回りが高そうだから」と安易に物件を選んでしまうケースです。例えば、地方の築古マンションは表面利回りが高く見えても、実際には入居が決まりにくく、空室が長引くこともあります。
また、駅から遠い、周囲に大学や企業がないといった立地の悪さも空室リスクを高めます。
さらに、築古マンションの場合は修繕費用のリスクも考慮しないといけません。人に置き換えて考えてみると、年齢を重ねるほど病気のリスクは高まり、医療費は高額となります。不動産において年齢は築年数であり、築年数が経過することによる台所、風呂場の故障や、給排水管故障などの高額修繕リスクが高まることを考えなければなりません。
利回りだけで判断せず、地域の需要や将来性、管理状況など総合的に見ることが大切です。
物件選びを間違えると、家賃収入が安定せず、修繕費や管理費ばかりがかかる「持っているだけで赤字」な状態に陥ってしまう恐れもあります。
知識がないまま不動産業者に任せたケース
不動産投資が初めての人は、不動産業者の言うことを鵜呑みにしてしまいがちです。「手間がかからず副収入になりますよ」といったセールストークに安心し、契約書の内容をよく確認せずに進めるケースも見られます。
よく受ける提案として、「老後年金」「保険」「節税」すべての効果が受けられるというものが挙げられます。確かに間違いではないのですが、物件選びを間違えてしまうと、本来の目的を果たせなかったり、効果としてパフォーマンスが悪い投資商品になってしまったりします。
また、売却相談の際、「どんな目的で不動産投資を始めたのか」という問いかけに対して、明確に回答できる方はわずかな印象です。
特に何か目的があるわけではなく、営業担当者に言われたままに買ってしまい、結果何のために投資を始めたのかを理解しないまま持ち続けてしまう方も多くいるのが現状です。
結果として、不利なローン条件や賃貸管理契約を組まされてしまったり、収益性の低い物件を高値で買わされていたりすることもあります。
また、管理や修繕のことを事前に確認していないと、予期しない支出に苦しむことになります。
信頼できる不動産業者選びはもちろんですが、自分自身でも知識を持ち、内容を理解したうえで判断する姿勢が不可欠です。
「サブリース=安心」と勘違いしたケース
サブリースとは、管理会社が物件を一括借り上げし、空室でも一定の家賃を保証してくれる仕組みです。一見安心に思えますが、実は「家賃保証」といっても永続的ではありません。
契約から数年で保証家賃が下がることもあり、途中解約が難しい長期契約になっているケースもあります。
また、保証家賃の見直しを一方的に通知され、収入が減ってしまったというトラブルも報告されています。
また、ご自身の裁量で入居者の募集賃料を決められるわけではなく、サブリース会社が空室リスク削減のために相場賃料よりも低い金額で貸し出してしまうケースもあります。仮にサブリースが解約できたとしても、想定していた賃料よりも大きく下回り、売却の際に利益が少なくなってしまうこともリスクとして考える必要があります。
こうしたことから、「サブリースなら安心」という考えは危険です。契約内容をよく確認し、万が一のリスクをしっかり把握しておくことが重要です。
ワンルームマンション投資が向いている人・向かない人

投資に向いているかどうかは、人それぞれの性格や状況によって異なります。ワンルームマンション投資も例外ではなく、成功している人には共通する特徴があります。ここでは、「どんな人に向いていて、どんな人には向いていないのか」を具体的に見ていきましょう。
1. ワンルームマンション投資が向いている人の特徴3つ
2. ワンルームマンション投資が向いていない人の特徴4つ
これから始めるか迷っている人は、自分がどちらに当てはまるかチェックしてみてください。
ワンルームマンション投資が向いている人の特徴3つ
【ワンルームマンション投資が向いている人の特徴】
1. 安定した収入があり、投資用物件のキャッシュフロー管理ができる人
2. 長期的な視点で資産を育てる姿勢を持っている人
3. 積極的に情報収集し、自分で判断する意識を持っている人
ワンルームマンション投資が向いているのは、まず安定した収入があり、投資用物件の収支バランスを適切に管理できる人です。例えば、会社員や公務員など、信用力が高く、金融機関からの投資用融資を受けやすい職業の人が該当します。家賃収入と諸経費、ローン返済のバランスを理解し、全体のキャッシュフローを把握できる人が成功しやすいでしょう。
また、すぐに結果を求めず、長期的な視点で資産を育てる姿勢を持っていることも重要です。家賃収入が安定するには時間がかかるため、焦らずコツコツと運用できる人が成功しやすい傾向にあります。思わぬ出費の代表例である空室や修繕費用などにも動じずに、リスクを事前に確認した上で許容範囲を広げておく必要があります。
さらに、投資に関して積極的に情報収集し、自分で判断する意識を持っている人も向いています。信頼できる情報を見極め、自ら学び続けられる人ほど、失敗のリスクを下げられます。
ワンルームマンション投資が向いていない人の特徴4つ
【ワンルームマンション投資が向いていない人の特徴】
1. 「すぐに儲けたい」と考える短期志向の人
2. 借金に強い不安を感じる人
3. 営業トークを鵜呑みにしてしまう人
4. 直近でマイホームの購入を検討している人
ワンルームマンション投資が向いていないのは、「すぐに儲けたい」と考える短期志向の人です。この投資は長期運用が前提なので、短期間で成果が出ないと不満を感じるタイプには不向きです。長期運用が前提なのは、老後年金として受け取るまでにはローンを完済する必要がある点や、売却をするにも5年以内の売却の場合は短期譲渡税が39.63%となり高額になるためです。
借金に強い不安を感じる人も注意が必要です。ローン返済には計画性が求められるため、返済に追われること自体にストレスを感じやすい人にはおすすめできません。
また、営業トークを鵜呑みにしてしまうのも危険です。「なんとなく安心そう」といった理由で契約してしまうと、あとで後悔する可能性が高くなります。
自分で情報を確認せず、判断を他人任せにする姿勢は、投資では大きなリスクになります。
そしてもう一つは、直近で自宅購入を考えている場合、与信枠の兼ね合いで、自宅購入の際にローンの借入条件が悪くなってしまったり、そもそもローンを組めなくなったりという状況にもなりかねません。直近で自宅を購入する予定がある場合には、しっかりと資金計画を立てる必要があります。
ワンルームマンション投資で成功している人の特徴と投資スタンス

同じワンルームマンション投資でも、成功する人と失敗する人では「考え方」や「行動」に大きな差があります。では、どんな人がうまくいっているのでしょうか?最後に、実際に成果を出している人の特徴や、共通する投資スタンスについて紹介します。
● 長期的な視点で計画を立てている
● 情報収集と勉強を欠かさない
● 信頼できる不動産会社と付き合っている
自分の投資スタイルを見直すきっかけにもなるはずです。
長期的な視点で計画を立てている
成功している人の多くは、ワンルームマンション投資を「長期戦」として捉えています。すぐに儲けようとはせず、10年、20年といったスパンで安定した家賃収入を得ることを目指しています。また家賃収入ではなく売却益を目指している方も、前述した譲渡税の兼ね合いで、原則として最低でも5年以上の保有がおすすめされています。
そのため、物件選びも「すぐに稼げるか」ではなく「将来まで価値を保てるか」を重視します。
具体的なポイントとしては、検討物件の
● 家賃は適正であるか
● 管理費修繕積立金は適正であるか
● 総戸数は少なくないか
● マンション借入がないか
● 最寄駅から遠くないか
● 近くに嫌悪施設はないか
などを重視している傾向にあります。また、修繕や管理の費用も計算に入れ、収支計画をしっかり立てています。
一時的な利回りに惑わされず、長く持ち続けられるかどうかを見極める姿勢が、結果として成功につながっているのです。
情報収集と勉強を欠かさない

成功している投資家は、とにかく「勉強熱心」です。不動産の仕組みや融資の仕方、税金、エリア特性など、自分なりに情報を集めて理解を深めています。
書籍やセミナーだけでなく、実際の投資家の体験談や、失敗例からも学んでいる人が多いです。
また、複数の営業担当者から話を聞くことも重要です。成功している人は、さまざまな不動産会社の人の情報を聞き、何が正解なのかを勉強しています。
そのため、営業トークにも惑わされることなく、自分の基準で判断する力が身についています。
情報を集めて終わりではなく、「比較する力」「選ぶ力」「断る力」も磨いていくことが、成功への近道になっているのです。
信頼できる不動産会社と付き合っている
ワンルーム投資で成功している人は、良いパートナーを持っていることが多いです。なかでも、不動産会社の選び方はとても重要です。
信頼できる会社は、物件のメリットだけではなく、リスクやデメリットについても正直に話してくれます。また、購入後の管理・入居対応・修繕の相談までトータルでサポートしてくれる体制が整っています。
逆に、営業トーク一辺倒で契約を急かすような会社は要注意です。長く付き合えるパートナーとして、自分に合った不動産業者を選ぶことが、成功を左右する大きなポイントになります。
下記の記事では、信頼できる不動産投資相談先の選び方を解説していますので、気になる方はあわせてチェックしてみてください。
不動産投資のおすすめ相談先6選!選び方や相談時に押さえるべきポイントを紹介
大切なのは、自分に合った投資戦略を選ぶこと

ワンルームマンション投資は、たしかに「やめとけ」と言われる要素も存在します。収益性の低さや空室・家賃下落のリスク、出口戦略の難しさなど、慎重になるべき点は多くあります。
しかし、それだけで「絶対にやめたほうがいい」と決めつけるのは早計です。利益を生み出しにくいといわれているワンルームマンションでも、成功している投資家は数百万円単位で利益を出しているのが実情です。
正しい知識を身につけ、信頼できるパートナーと組み、長期的な視点で投資できる人にとっては、有効な資産形成手段にもなり得ます。
大切なのは、自分の資金状況や目的に合った方法を見極めることです。リスクを理解したうえで、冷静な判断を下せるように、学びを重ねていきましょう。
なお、ノムコム・プロに会員登録すると「新着物件」や「サイト非公開物件」などの情報をメールで受け取れるほか、無料で会員限定物件の閲覧もできます。下記リンクから登録のうえ、ぜひノムコム・プロの会員特典をご活用ください。









