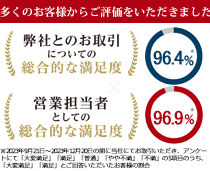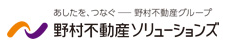共有名義の不動産とは、数人が共同で所有する不動産のことです。共有名義不動産の場合、単独では売却できず、共有者全員の同意と必要書類の提出が必要になります。さらに、売却の方法や手続きを誤れば、共有者間で売却益や税金、費用に関してトラブルを伴うことも少なくありません。
そこで本記事では、共有名義不動産の概要や売却方法や、スムーズに進めるためのポイントを解説します。共有名義不動産を所有する方や売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
1. 共有名義不動産とは
共有名義不動産とは、複数人が共同で所有している不動産のことです。共有者それぞれの所有権を「持分:もちぶん」という形式で数値化し、各共有者がどの割合で所有権をもっているかが明確にしています。例えば、2名の共有者の所有権がそれぞれ50%ずつであれば、持分1/2ずつで共有といった形です。
共有名義の不動産は、固定資産税および都市計画税などの税金や、維持管理のための管理委託料および水光熱費などの管理実費、売却した際の売却金や売却にかかった経費など、利益や損失および経費などのすべてを持分に応じて按分(あんぶん:基準となる数量に比例して割り振ること)するのが基本です。
また、共有名義の不動産は、一部の共有者だけで勝手に全体を一括売却することはできません。共有不動産全体を売るには、共有者全員の同意が必要です。一方で、自身が保有する持分だけなら単独で売却できます。ただし、他の共有者がいる共有不動産では、買い手探しの難易度が高いため、実務上、共有持分のみの売却はあまり見かけません。
不動産が共有名義になるケースは、共同相続や共同購入などさまざまです。以下で、共有名義不動産の具体的な状況や売却の特徴について解説します。
1-1.不動産を共有名義にする状況
不動産が共有名義になる状況としては、共同購入や共同相続、共有持分の購入があります。
不動産の共同購入では、夫婦それぞれが住宅ローンを組んで住宅を購入する「ペアローン」や、親子間で住宅ローンを連携して住宅を購入する「リレーローン」があります。
他方、不動産の共同相続とは兄弟や姉妹で親の不動産を共同で相続する場合です。もともと単独所有だった不動産の所有権持分を購入することで、共有名義になる場合もあるでしょう。
なお、共有持分が1/2や1/3しかないときでも、共有者は共用名義の不動産の全部を使用することができ、自分の持分だけを単独で自由に処分できます。また、法律により、共有名義の不動産の修繕といった「保存行為」を単独で行うことも認められています。ただし、改装工事や賃貸借契約の解除といった「改良行為や共有物の利用に関すること」は、各共有者の持分の価格の過半数の同意がないと行えません。
1-2.共有名義不動産の売却の特徴
共有不動産の全部を一度に売却するときは、原則、共有者全員の同意が必要です。ただし、売却価格や売却タイミングは、共有者により考え方が異なる場合があり、その調整には時間がかかることも少なくありません。
2. 共有名義不動産の売却方法・3つ

共有名義の不動産を売却する方法は、主に以下の3パターンです。
2-1.共有者全員の同意を得て売却する方法
もっとも一般的でおすすめなのが、共有者全員の合意を得て不動産全体を売りに出す方法です。全員が売却に同意するのであれば、単独所有不動産の売却と同じで売却しやすく、価格も高額になりやすいでしょう。
2-2.土地を分筆してから売却
土地の分筆や建物の分割など不動産を物理的に切り離せるなら、単独名義で自由に売却できる状態が作り出せます。ただし、法的手続きや費用負担が大きく、建物は物理的に分割が難しい場合のほうが多いため、難易度の高い方法です。
2-3.自己の持分のみを売却する方法
共同相続した不動産を売却するときに、共有者全員の同意がなかなか得られない場合には、自分の持分だけを売却することも可能です。
2-3-1.ほかの共有者へ自己の持分を売却する方法
ほかの共有者に、自分の持分を買い取ってもらう方法です。ただし、共有不動産が高額である場合には、買い取るための資金調達が必要になる場合もあるでしょう。しかし、必ずしもローンが組めるとは限らないため、これも難易度の高い方法です。
2-3-2.共有者でない第三者へ自己の持分を売却
第三者に自分の共有持分を買い取ってもらう方法です。ただし、一般的には共有不動産の一部だけを積極的に買う方は希少であり、難易度が高い方法です。こういった背景から、共有持分専門の買取業者が買主となるケースも多く、価格が格安になりがちです。
この場合、買取業者が他の共有者へさらなる買い取りを求めたり、分割請求という裁判手続きを行ったりする場合もあるため、トラブルに発展するリスクも考慮しておきましょう。
3. 共有名義不動産を売却する手続きの流れ
不動産仲介会社が共有名義不動産を売却する手続きの一般的な流れは、以下の表の通りです。売却手続きを行う代表者を決めて不動産会社との対応窓口にするとスムーズに進むでしょう。
共有名義不動産を売却する手続きの流れ
|
(1)不動産の査定 |
複数の不動産会社へ売却査定を依頼する |
|
(2)媒介契約の締結 |
不動産会社と売主との間で、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介のうちいずれかを選んで締結 |
|
(3)販売活動 |
募集広告、内覧立会、購入申込書の受領、条件の調整、価格交渉 |
|
(4)売買契約の締結 |
売買契約書を取り交わし手付金を受領 |
|
(5)残金決済 |
売買代金を受領し書類やカギなどを引き渡す |
|
(6)不動産登記の申請 |
司法書士が代行するのが一般的 |
|
(7)確定申告 |
売却月の翌年の2/16?3/15に税務署へ申告 |
4. 共有名義不動産の売却に必要な書類と費用
共有名義不動産の売却では多くの書類が必要であり、いくつもの費用が発生します。
4-1不動産の売却に必要な書類
不動産の売却に必要な売主の書類および留意点は、以下の表の通りです。
不動産の売却に必要な売主の書類
|
本人確認書類 |
運転免許証やパスポートなど写真付の身分証明書が望ましい |
|
権利証(登記識別情報) |
不動産を売却する際の売主本人の証明や所有権移転登記手続きに必須 |
|
固定資産税評価証明書 |
自治体が不動産評価額を示した書類で、自治体の役場などで取得する |
|
住民票 |
住所変更登記で必要、氏名変更の場合は戸籍の附票が必要になる場合あり |
|
不動産売買契約書 |
今回売却する不動産を購入した時点の売買契約書 |
|
実印 |
売買契約書の締結や登記申請手続きに使用する |
|
印鑑証明書 |
同上 |
|
領収書 |
売買代金の受領書、通常は不動産会社が用意する |
関連記事【不動産売却とは?売却までの流れと方法|家や土地を売るときに知っておくべき手続きと注意点】
4-2.不動産の売却でかかる費用
不動産の売却でかかる費用および留意点は、以下の表の通りです。
不動産の売却に必要な売主の費用
|
仲介手数料 |
法定上限額は売却価格の3%+6万円(消費税別途) |
|
司法書士報酬 |
司法書士の登記申請代行料、マイホームの決済や登記手続きなら10万円前後が相場 |
|
印紙税 |
売買契約書に貼付して納税 |
|
登録免許税 |
所有権移転登記の際に納税が必要な税金で、不動産登記申請書に添付する |
|
譲渡所得税 |
売却益があった場合、所得機関によって税率が異なる |
|
住民税 |
売却益(譲渡所得)が生じた場合に課税される、所有期間によって税率が異なる |
5. 共有名義不動産の売却における注意点

共有名義不動産の売却では、共有者全員の意見を確認しながら進めることが重要です。
5-1.共有者間の意見調整
共有名義の不動産全体を一括で売却するためには、共有者全員の売却への同意が必須です。まずは「売却するか否か」そして「誰が中心になっていつから売り出すか」など、共有者全員の意思確認を行いましょう。
5-2.税金や費用の負担
不動産の売却では、さまざまな費用や税金の出費がつきものです。共有者の誰がどの費用をどの程度負担するのかを決めて、費用清算のトラブルを未然に防ぎましょう。
また、仲介手数料や司法書士報酬、印紙税、登録免許税などは現金一括払いが基本であるため、支払い期日までに資金調達ができるよう確実に手配すべきです。もし、合意が得られて売却になるなら、売出時期や売出価格、売却価格の最低ラインなどの負担を要することも話し合う必要があります。
5-3.売却益の分配
共有不動産を売却して得たお金やかかった経費は、共有者の持分割合に応じて按分して分配・負担するのが原則です。持分1/2ずつ共有している土地建物の売却益が3,000万円、売却経費と修繕費用の合計が300万円なら、売却金は1,000万円ずつ分配して経費は100万円ずつ負担します。
5-4.トラブル防止策
売却活動が長期化すると、共有者の一部が「もっと高く売ってほしい」「やっぱり売りたくない」と言い出したり、ほかの共有者もしくは共有持分買取専門業者へ自分の持分だけ先に売ったりしようとする可能性も出てきます。
売却期間に応じた価格変更や値下げ交渉に応じる最低価格など、特に重要な事項は合意書面にして残しておくと安心です。途中で意見が分かれないよう、全員が納得した形で売却活動を続けていきましょう。
6. 共有名義不動産をスムーズに売却するポイント
共有名義不動産の売却では、複数の共有者が協力して売却活動を進めなくてはなりません。ここでは、手続きを滞りなく進めるためのポイントをご紹介します。
6-1.共有持分権者を特定する
まずは、誰がどの不動産にどれくらいの持分を所有しているかを正確に確認しましょう。不動産ごとの権利関係は、最新の登記事項を閲覧すれば簡単で正確に把握できます。ただし、相続手続きを終えていない場合は思わぬ共有者が出てくる場合もあります。相続登記が未了の場合は、先に調査を行って相続財産の範囲や相続人を確定させるところからはじめましょう。
6-2.手続き窓口を誰にするか決める
共有名義不動産の売却では、手続きする人を決めておくと、手続きが進みやすいです。例えば、共有者の一部が遠方に住んでいたり、仕事や病気で契約や代金決済、隣地境界指示の場などに立ち会えなかったりする場合、ほかの共有者へ、委任状を託して手続きを代行してもらいましょう。この委任状には、実印を捺印し、印鑑証明書を添えるのが一般的です。
なお、認知症等の症状が現れた成年被後見人が共有不動産を売却するときは、成年後見人が成年被後見人を代理して手続きを進めることになります。共有者の一人が成年後見人の場合は、成年被後見人の成年後見人であることを証明する、登記事項証明書を準備するのが一般的です。
共有者全員で立てた手続きの代表者が単独で売約手続きをすれば、コミュニケーションが一元化できスピーディーに手続きが進みます。ただし、代表者に都合が良いよう勝手に決めたと勘違いされないよう、書面で事前に合意を得たり、定期的に情報共有を行ったりして進めましょう。
6-3.事前に費用負担の割合を決める
売却には仲介手数料や司法書士報酬、リフォームや解体費、ローンの残債、税金など多様な費用がかかります。誰がどの費用をどの割合で負担するのか、事前に決めて書面に残しましょう。
6-4.最低売却価格を決める
相場とかけ離れた売出価格では、売却期間が長引く可能性が高まります。まずは、売却相場を正確に把握しましてください。そして、共有者全員が納得できる最低売却価格を設定し、値下げ交渉に備えましょう。正確な売却相場を知るためには、複数の不動産会社へ査定を依頼し、複数の意見を比較してみてください。
6-5.専門家のサポートを受ける
共有名義不動産の売却では、地域の相場を熟知した不動産会社をはじめ、弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士などの専門家の協力が欠かせません。費用を抑えようと自力で頑張った結果、思わぬトラブルに遭うこともあるため、共有名義不動産は専門家のサポートを受けながら売却することをおすすめします。
7. 共有名義不動産の売却におけるトラブル事例と対処法
共有名義不動産の売却では意見の対立が起こりやすいものです。あらかじめトラブル事例を頭に入れ、問題が起こりそうなら、早めに専門家を間に入れて話し合いましょう。
7-1.共有者の一部が売却に反対するケース
共有者の一部が「まだ住み続けたい」「価格が安すぎる」「費用を負担したくない」などと言って反対することもあるでしょう。こういった場合は、放置して交渉が長引くほど懐疑的で感情的になりやすい傾向にあります。早期に、不動産に詳しい専門家を交えて、話し合いをするのがおすすめです。
7-2.共有持分のみが第三者に売却された場合
共有者の一人が自分の持分を無告知で第三者(買取業者)へ売却した場合、新たな共有者である買取業者が高額で持分を買い戻させようとする場合があります。買取業者が共有者になった場合、トラブルになるかもしれないので、早期に、弁護士へ相談するのがおすすめです。
7-3.共有物分割請求への対応
買取業者が「共有物分割請求訴訟」を行って、強制的に不動産を売却させようとする場合がありますが、共有物分割請求自体は法律上認められた権利であり、やむを得ない事情がない限り拒否できません。ただし、話し合い(任意協議)が平行線のままなら、調停や訴訟へと進み長期化する可能性もあります。早期に弁護士などを交えて対応を検討しましょう。
8. 不動産を共有名義にしないためのポイント
共有名義不動産は、売却時だけでなく、管理や修繕などでも意見の衝突が起きやすいと言えます。トラブルにならないように、最初から共有名義にしないことも大切です。以下のポイントも覚えておきましょう。
8-1.夫婦ペアローンや親子リレーローンに注意
融資可能額を増やしたい、収入がある家族が協力して楽に返済したいという理由で、夫婦や親子のローンを組むケースは少なくありません。しかし、万一の離婚や家族関係の悪化で不動産を処分したくても、夫婦や親子の相手方の持分買取やローン負担者の変更は簡単ではありません。
8-2.遺産分割時に共有名義にしない
相続人間の公平を意識して共有名義で相続するケースがありますが、不動産を共有名義にすると、維持管理や不動産活用、売却などが難しくなる可能性が高まります。まずは共有名義にしないことを前提に、遺産分割協議を行いましょう。
8-3.共有不動産のことは弁護士に相談
すでに不動産が共有状態でトラブルが不安なら、はじめから弁護士に相談するのが得策です。弁護士が付くと相手への牽制効果があり、手続きや交渉を間違うこともなくなります。トラブルが深刻になる前に、弁護士へ相談しましょう。
9. 共有名義不動産の売却でよくある質問

ここでは、共有名義不動産の売却でよくある質問とそのポイントを整理します。
9-1.共有不動産の売却にはどんな方法がある?
共有不動産の売却方法は大きく3つに分かれます。
- 共有者全員の同意を得て不動産全体を売却する
- 自分の持分だけを売却する
- 土地を分筆したうえで売却
9-2.共有不動産の売却には共有者の同意が必要?
はい、共有不動産の売却には、原則共有者の同意が必要です。売却することに同意が得られたとしても、売却のタイミングや売出価格については、それぞれの共有者で異なることが考えられます。事前に何パターンかプランを立て、頭の中を整理しておくと良いでしょう。
9-3.共有不動産の売却代金の分配や諸経費と税金の負担はどうする?
特別な取り決めがない場合は、売却代金や諸経費はその持分に応じた割合で分配したほうが、分配根拠が明確なので、一番トラブルになりにくいでしょう。事前に行う不動産売却査定の価格などから、おおよその分配金額も算出可能です。
9-4.共有者が不動産の売却に反対した場合は?
以下のような対応策があります。
- 反対の理由を聞いて、価格調整や費用負担の工夫で合意を目指す
- 反対者の持分を他の共有者が買い取る
- 共有物分割請求という法的手続きで強制的に共有状態を解消する
9-5. 共有名義不動産を売却する際の注意点とは?
以下のような点に注意しましょう。
- 共有者全員が一堂に会して十分に話し合い、意思統一を図る
- 不公平感や疑念がないよう、費用や売却益を詳しく説明する
- 自力解決が困難なら、不動産会社や弁護士などプロに相談する
10. まとめ
共有名義不動産の売却では、売却金や諸費用、税金などの配分などを持分比率に応じて調整するのが基本です。そして、売却を成功させるには共有者全員の同意と協力体制が欠かせません。円滑な手続きのためには、事前に費用負担を明確にして手続き担当を一人にするなど、事前の綿密な準備がスムーズな売却のカギとなるでしょう。

宅地建物取引主任士、管理業務主任者
司法書士事務所に2年、大手不動産管理会社に5年、個人顧客を中心に不動産賃貸・売買の仲介営業会社に7年間従事。また、外資系金融機関にも2年間従事し個人顧客へ金融資産形成や相続税の節税アドバイスなどを担当。現在は不動産/金融業界での経験を活かし、記事を執筆にもあたっている。
あわせて読みたいコラム5選
不動産売却・住みかえをお考えなら、無料査定で価格をチェック!
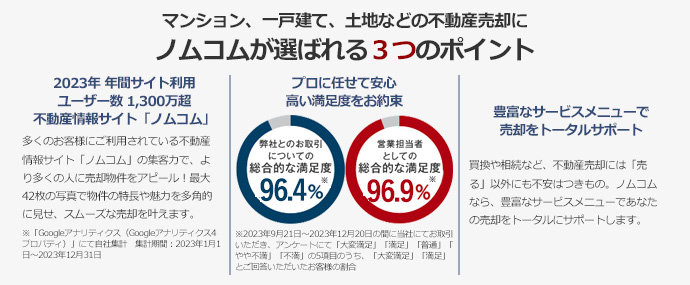
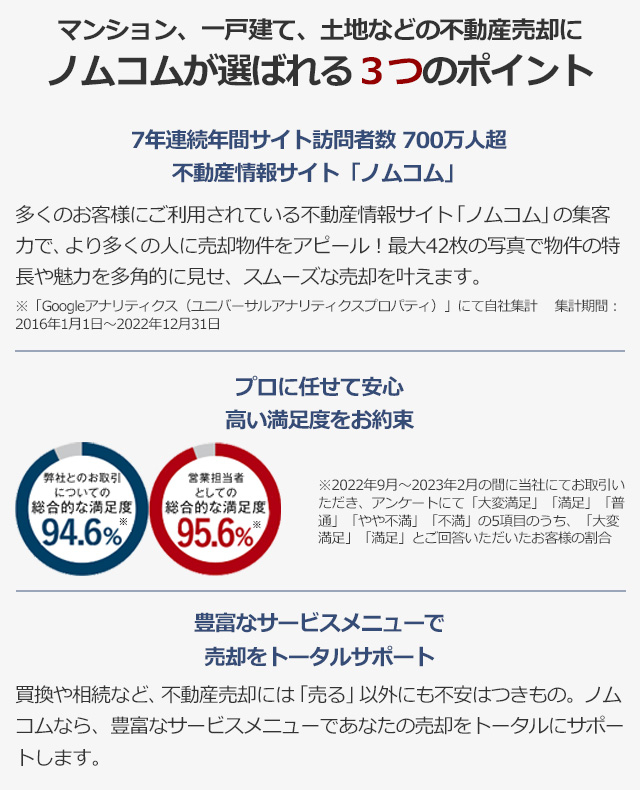
新着記事
-

2025/04/16
共有名義の不動産売却|プロが教える!トラブルを防いで賢く売る方法
-

2025/04/04
土地が売れるか知りたい!売れる土地/売れない土地の特徴&対策
-

2025/04/03
土地の売買は個人間でも可能!手続き方法や注意点、メリット・デメリットを解説
-
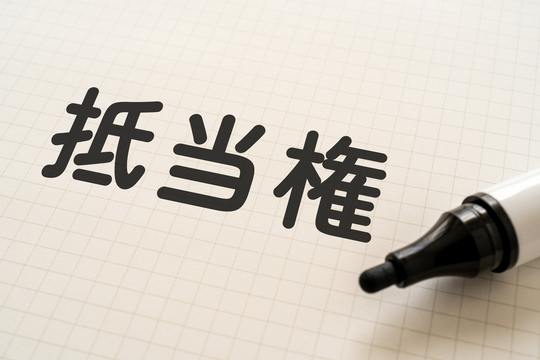
2025/04/03
抵当権抹消費用は不動産1件につき1,000円|自分で手続きする方法や注意点を解説
-

2025/03/31
家の価値を調べる方法や注意点「高い=良い」ではない!をプロが解説
-
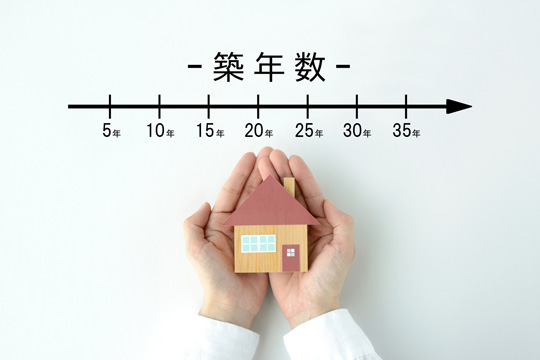
2025/03/31
戸建ての寿命は何年?延命のコツやリフォーム/建て替えについても解説
人気記事ベスト5
不動産売却ガイド
- 最初にチェック
- 不動産の知識・ノウハウ
- 売却サポート
- Web上で物件を魅力的に魅せる! サポートサービス
- お買いかえについて
- お困りのときに
カンタン60秒入力!
売却をお考えなら、まずは無料査定から
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ