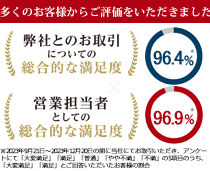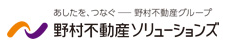「用途地域」とは、都市計画法において、居住、商業、工業など、土地の利用目的に応じて13種類に区別した地域のことです。これにより、地域ごとに建築可能な建物の種類や、用途が制限されています。この記事では、宅建士の資格をもつ筆者が、用途地域の基本的な概念から、各地域の特徴、指定の土地がどの用途地域に該当するかを調べる方法などを詳しく解説しています。不動産購入における用途地域確認の重要性も紹介しているので、用途地域について知って、適切な場所にマイホームを建てていきましょう。
<<カンタン60秒入力!不動産無料査定で価格をチェックしてみる>>
1. 用途地域とは

都市づくり・街づくりでは、どのような建物を建てて良いか、ルールが決められており、用途地域の指定もそのひとつです。
1-1.用途地域とは
用途地域とは、「都市計画において、市街化を促進していこう」と指定された地域内において、街並み・地域に特色をもたせることで、住環境を保護したり、利便性を促進したりするための「エリア分けルール」です。各市町村の長が、専門家で構成される審議会等で意見を求めて決定します。
1-2.用途地域で定められるルール
各用途地域によって定められたエリア内では、容積率や建ぺい率、高さの制限、建てることができる建物の種類が決まっています。このようなルール決めにより、住居地域・商業地域・工業地域のすみわけを実現しているのです。
1-3.都市計画法上のさまざまな区分
用途地域は、すべての地域に定められているわけではありません。都市計画法では、各市区町村の土地を都市計画において「都市計画区域」「準都市計画区域」「それ以外」に区分し、都市計画区域はさらに「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」に分けられます。用途地域は、原則として市街化区域に指定される区分です。
2. 13種類の用途地域

用途地域は住居系・商業系・工業系に分かれており、全部で13種類の用途地域があります。どの用途地域に指定されているかにより、周辺建物の種類や高さ、住環境が変わってきます。
2-1.第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域は、住宅の高さが10-12mに制限されており、戸建てや低層マンションが中心となっている地域です。事務所や店舗は住居と兼用となっている場合のみで、床面積も50㎡以内という制限があります。高い建物は学校くらいしかありません。建ぺい率・容積率もかなり制限されているため、2階建ての戸建てやアパートが立ち並ぶような街並みとなります。
2-2.第二種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域は、高さや建ぺい率・容積率は第一種と同様ですが、小規模の店舗の建築が認められています。そのため、一戸建ての住宅街のなかにコンビニや喫茶店、美容室などが点在するようなイメージのエリアになります。第一種低層住居専用地域よりもいくぶん利便性が増したエリアと言えるでしょう。
2-3.田園住居地域
田園住居地域は、平成30年4月に新しく創設された13番目の用途地域です。高さは第一種と同様ですが、緑地や田畑との調和から農業向けの小規模施設の建築が可能となっています。都市部の緑地(農地)の中には、第一種・第二種低層住居専用地域のなかに存在するものもあり、農地として活用することが難しい土地もありました。このようなエリアを、新たに田園住居地域と指定することで農地との共存を図り、宅地への無秩序な転換を抑止しようとしたものです。
2-4.第一種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域は、住居の高さ制限はなく分譲・賃貸マンションが中心となるエリアです。イメージとしては、3階から5階程度のアパート・マンションが見られる街並みとなります。住居のほか、500㎡までの店舗や病院なども建設することができます。
2-5.第二種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域は第一種と同様住居の高さ制限はないため、分譲・賃貸マンションが中心となるエリアとなります。第一種との違いは1500㎡・2階建て以下の店舗・事務所が建築できるため、第一種よりは大きめのスーパーや飲食店、事務所、倉庫などの建物も多くなってきます。
2-6.第一種住居地域
第一種住居地域は、住環境を守りつつも商業施設との調和を図ったエリアです。3,000㎡までの店舗・事務所・ホテル等を建築できるエリアとなっており、やや広めの道路沿いのエリアをイメージするとわかりやすいかもしれません。
2-7.第二種住居地域
第二種住居地域は、住み良い住環境を保ちながら大規模な商業施設が隣接するようなエリアです。第一種住居地域よりもさらに大規模な商業施設(10,000㎡までの店舗・事務所・ホテル、ボウリング場、カラオケボックス、パチンコ店など)の建築が可能となっています。幹線道路沿いのエリアが多くなっています。
2-8.準住居地域
準住居地域は大きな国道など幹線道路沿いが中心の住居地域です。第二種で認められている大規模な商業施設のほか、倉庫業向けの倉庫や小規模な自動車修理工場の建築が可能です。利便性は高いものの騒音や粉じんなどの住環境への影響もあります。
2-9.近隣商業地域
近隣商業地域は、店舗・事務所に床面積の制限がなく、ほとんどの商業施設の建築が認められています。駅前の商店街のようなイメージです。高層マンションと商業施設が混在するエリアもあり、にぎやかさと利便性を重視する人にとっては住み心地の良いエリアです。
2-10.商業地域
商業地域はほぼすべての商業施設、倉庫、事務所などの建築が可能なエリアです。ナイトクラブなどの風俗営業も可能なエリアであるためターミナル駅周辺地域をイメージすると良いでしょう。再開発等によって建築された高層マンション等のほかは、住宅はあまり見られません。
2-11.準工業地域
準工業地域はアパート・マンションなどの住居と中小規模の工場が混在する地域です。商業施設や事務所の制限もないため、近年では職住近接の考え方により再開発が進んでいるエリアでもあります。古くからの工業地帯が再開発されてショッピングモールとマンションに生まれ変わっている地域もあります。
2-12.工業地域
工業地域は工場や倉庫がメインのエリアです。学校の建築が制限されるため、住居もそれほどありません。
2-13.工業専用地域
工業専用地域は、住居系の建物が建築できない工場がメインのエリアです。大規模な工業団地やコンビナート、化学工場など人体に危険を及ぼす可能性のある工業製品を製造する工場の建築まで認められています。
3. 用途地域の調べ方
用途地域は、都市計画図を入手することで調べることができます。市町村によっては、紙での販売は行っておらず、インターネットでのダウンロードのみのところもあるようです。用途地域マップなどの一覧をWebで確認できる地域もあるため、まずは市町村のホームページ等で確認してみましょう。
4. 用途地域の確認が重要である理由
用途地域の指定により、住環境の静かさやにぎやかさ、建物の高さや種類が違ってきます。つまり、住む場所がどの用途地域に指定されているかは「住み心地に直結」します。また、用途地域を調べるとともに、実際に現地を確認してみて、どのような地域なのかを肌で感じてみることも大切です。例えば準工業地帯に指定されていても、現地ではマンション開発が進み、住宅地域にさま変わりしているところもあります。
5. まとめ
用途地域は、エリアの特色を決める大切な建築ルールです。用途地域が表示された土地計画図を片手に街を歩いてみると、用途地域が変わるところで住宅の高さや、建物の種類が変化していることに気づくことでしょう。戸建て用の土地や建売住宅は、住居系の用途地域に指定されていることが多いです。一方、マンションについては、商業系や工業系の用途地域に建てられることもあります。新たに家を購入する際には、ライフスタイルに合った住環境かどうか、ぜひ、用途地域の指定についても調べてみてください。

宅地建物取引士
株式会社イーアライアンス代表取締役社長。中央大学法学部を卒業後、戸建・アパート・マンション・投資用不動産の売買や、不動産ファンドの販売・運用を手掛ける。アメリカやフランスの海外不動産についても販売仲介業務の経験をもち、現在は投資ファンドのマネジメントなども行っている。
あわせて読みたいコラム5選
不動産売却・住みかえをお考えなら、無料査定で価格をチェック!
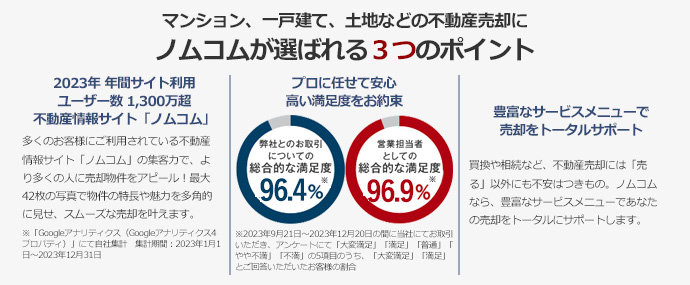
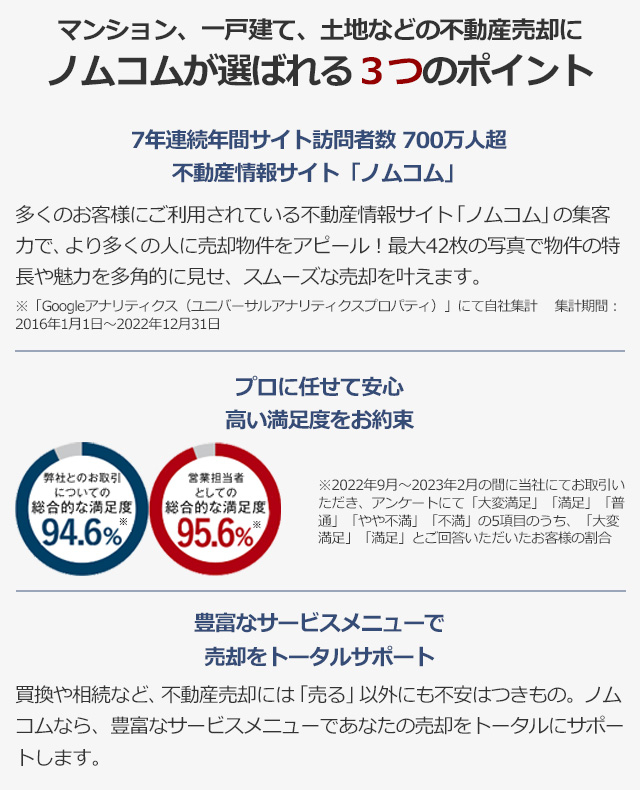
新着記事
-

2025/04/16
共有名義の不動産売却|プロが教える!トラブルを防いで賢く売る方法
-

2025/04/04
土地が売れるか知りたい!売れる土地/売れない土地の特徴&対策
-

2025/04/03
土地の売買は個人間でも可能!手続き方法や注意点、メリット・デメリットを解説
-
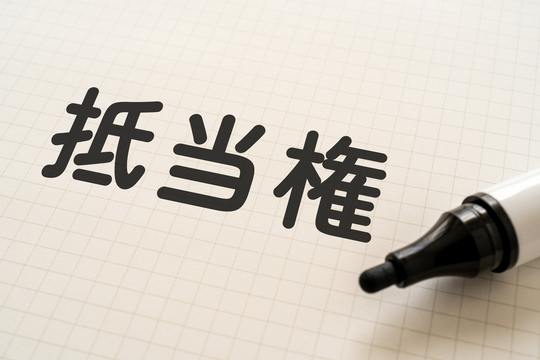
2025/04/03
抵当権抹消費用は不動産1件につき1,000円|自分で手続きする方法や注意点を解説
-

2025/03/31
家の価値を調べる方法や注意点「高い=良い」ではない!をプロが解説
-
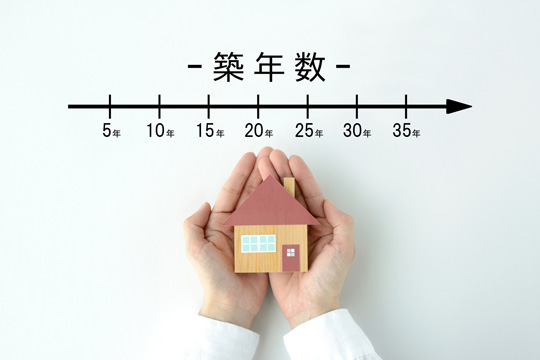
2025/03/31
戸建ての寿命は何年?延命のコツやリフォーム/建て替えについても解説
人気記事ベスト5
不動産売却ガイド
- 最初にチェック
- 不動産の知識・ノウハウ
- 売却サポート
- Web上で物件を魅力的に魅せる! サポートサービス
- お買いかえについて
- お困りのときに
カンタン60秒入力!
売却をお考えなら、まずは無料査定から
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ